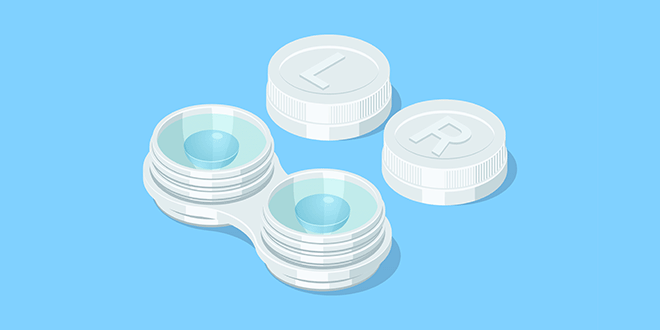
コンタクトレンズ業界の動向や現状、ランキングなどを研究しています。データは2022-2023年。コンタクトレンズ業界の過去の市場規模の推移グラフをはじめ、各社の売上高の推移やコンタクトレンズ業界の潮流などを解説しています。
業界規模
0.1兆円
成長率
4.6%
利益率
2.0%
平均年収
533万円
コンタクトレンズ業界の過去の業界規模の推移を見ますと、2020年には若干の減少となりましたが、中長期的には上昇傾向にあります。
コンタクトレンズ業界の動向と現状を見ていきましょう。下のグラフは、大手コンタクトレンズ4社の売上高の推移を示したものです。
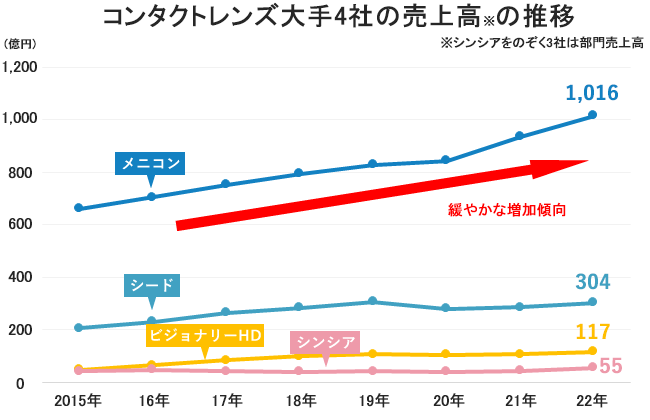
コンタクトレンズ大手4社の売上高の推移(各社公表資料より、グラフは業界動向サーチが作成)
グラフによると、2019年まで全体的に増加傾向にありましたが2020年には減少、2021年、2022年には再び増加傾向にあります。コンタクトレンズ各社の2022年の売上高は、メニコンが前年比8.5%増、シードは6.3%増、ビジョナリーHDは8.3%増、シンシアは22.2%の増加でした。近年では首位のメニコンが2位以下の売上高を引き離す流れとなっています。
2020年は新型コロナの影響で、コンタクトレンズ各社の売上が減少しました。外出自粛による来店を控える動きや、ショッピングモール等の営業自粛や短縮による影響と見られます。海外においても、代理店に対する出荷が大幅に遅れるなど悪い影響が出ています。
2022-2023年のコンタクトレンズ業界は、昨年に続き増収となっています。2021年後半からの経済再開の動きが、コンタクトレンズ需要の回復につながりました。アジアを中心とした海外売上高の増加も業績を後押ししています。
コンタクトレンズは視力を矯正するための医療機器に分類されます。視力の問題には近視、遠視、老眼とありますが、近年は、日本や中国、東南アジアにおいて近視人口が著しく増加しています。特に、スマホやゲームの普及に伴い、若年層の近視が進んでいます。
近年のコンタクトレンズ業界は拡大傾向にあります。国内、海外ともに販売が伸長しており、とくに1日使い捨てコンタクトレンズの「1DAY」が伸びています。遠近両用コンタクトレンズについては、ピント調整機能である「マルチフォーカル」の性能が向上しています。また、若年層には「カラーコンタクト」や「サークルレンズ」が人気を集めており、美容の一部としてコンタクトレンズを考える人も増えています。
※はコンタクトレンズ関連の部門売上高。2022-2023年のコンタクトレンズ業界の売上高ランニングを見ますと、首位はメニコン、シード、ビジョナリーHDと続きます。
メニコンは国内最大手のコンタクトレンズメーカーで、定額制会員「メルスプラン」に強みがあり、会員数は130万人を突破しています。シードはコンタクトレンズメーカー大手で、1日使い捨てレンズに強みがあります。
2022-2023年のコンタクトレンズ業界は、大手5社中4社が増収、1社が横ばいとなっています。全体としては前年から増加で推移しています。

コンタクトレンズ業界の最新の潮流や動向を、各社の取り組みと合わせてご紹介します。
業界大手のメニコンは、近年伸びている「1DAY」コンタクトレンズの販売拡大を継続します。「1DAY」コンタクトレンズは年平均成長率が18%にのぼり、メルスプランの「1DAY会員」も増加傾向にあります。
さらにメニコンは、Mojo Vision Incと「スマートコンタクトレンズ」の共同開発契約を締結しました。「スマートコンタクトレンズ」とは、拡張現実(AR)を利用し、映像や文字を提供する次世代コンタクトレンズです。
拡張現実(AR)を利用したスマートコンタクトレンズ「Mojo Lens」
砂粒程度のディスプレイをコンタクトレンズに埋め込むことで、拡張現実を実現することが可能となります。
シードは日本初の「EDOF(拡張焦点深度型)」コンタクトレンズを発売開始。EDOFコンタクトレンズは、遠近両用タイプのコンタクトレンズで、従来生じていたピントのずれを修正し、見える範囲を広げることに成功しました。
さらにメニコンやシードは、世界的に注目されている「オルソケラジーレンズ」を強化しています。「オルソケラジーレンズ」とは、寝る前に装用することで、寝ている間に近視を矯正する角膜矯正用コンタクトレンズです。いずれも海外で事業を開始し、近年では中国で高い成長が続いています。
美容・服飾雑貨を展開する粧美堂は「コスメコンタクトレンズ」を強化。派手過ぎず瞳に馴染むナチュラルなカラーが人気で、日本に加え、2019年から中国のEC事業を強化しています。カラーコンタクトレンズ市場は近年、若年層を中心に人気がある注目の分野です。
今後、コンタクトレンズ業界は、アジアでの底堅い需要を背景に拡大を続けるでしょう。さらに、角膜矯正や拡張現実(AR)、カラーコンタクトなど新しい市場の可能性も感じられます。今後の動向に注目が集まります。
コンタクトレンズ業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することでコンタクトレンズ市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
※メニコンはビジョンケア事業、シードはコンタクトレンズ・ケア用品事業、ビジョナリーHDはコンタクトレンズ+備品事業、粧美堂はコンタクトレンズ関連事業、フリューはコンタクトレンズ関連事業の売上高です。シェアとはコンタクトレンズ業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することでコンタクトレンズ市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれコンタクトレンズ業界の詳細ランキングページにジャンプします。
コンタクトレンズ業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
メニコン、シード、ビジョナリーHD、シンシア、粧美堂、フリューの計6社
コンタクトレンズ業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。コンタクトレンズ業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。