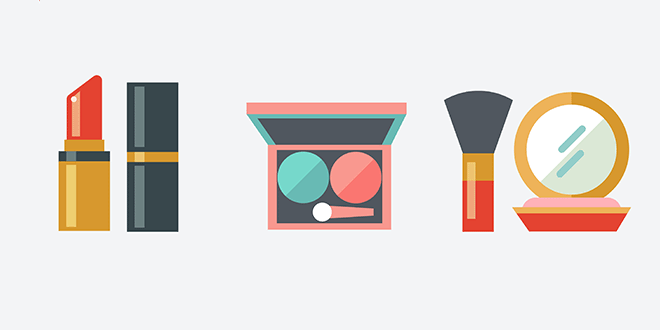
化粧品業界の動向や現状、ランキング&シェアなどを研究しています。データは2022-2023年。化粧品業界の過去の市場規模の推移をはじめ、化粧品出荷額の推移グラフや各社の新しい取り組みなどを解説しています。
業界規模
2.2兆円
成長率
-3.2%
利益率
2.2%
平均年収
595万円
化粧品業界の過去の業界規模の推移を見ますと、2020年に大幅に減少しましたが、近年では回復傾向にあります。
経済産業省の生産動態統計年報(2023年6月公表)によると、2022年の化粧品出荷額は前年比9.4%減の1兆2,654億円となりました。3年連続の減少です。
化粧品市場は右肩上がりで推移し、19年には初の1兆7千億円を突破、4年連続で過去最高額を更新しました。一方2020年以降は3年連続で下落、2022年はピークの19年から4,957億円が減少しています。
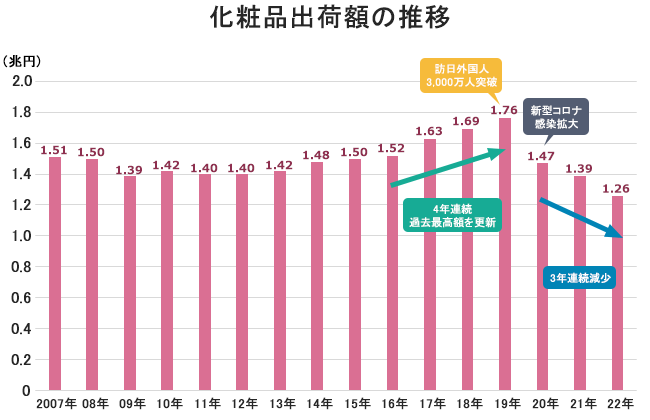
化粧品出荷額の推移(出所:生産動態統計年報、グラフは業界動向サーチが作成)
品目別出荷額の構成比を見ますと、化粧水や乳液等の「スキンケア用品」が45%と、全体の半数を占めています。シャンプーやリンス等の「頭髪用化粧品」は29%、ファンデーションや口紅などの「仕上げ用化粧品」は19%、残りは日焼け止めや香水などになります。
2022年の化粧品業界の動向をみますと、国内では行動制限の緩和により外出の機会が増え、口紅やリップの需要が前年に比べ増加しました。また、販売チャネルでは対面型も徐々に回復、年の後半以降は中価格帯商品においても回復傾向にあります。
海外市場では、経済活動の再開が本格化した欧州や米州で、化粧品需要の回復が見られたほか、空港などの免税店の業績も好調でした。一方、中国市場はロックダウンの影響により厳しい状況が続きました。
化粧品は販売チャネル数が多く、なかでも百貨店が化粧品業界の売上を牽引しています。ですが、2020年から2021年は中国人を中心とした訪日外国人が大幅に減少、百貨店の化粧品売上も大幅に下落しました。一方、2022年10月にはビザなし個人旅行が解禁されたこともあり、2022年の化粧品売上は前年比9%増(日本百貨店協会)となりました。2019年の水準から約7割の回復です。
国内の化粧品メーカー売上高のランキングでは、1位は資生堂、2位がコーセー、3位が花王となります。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | |
| 1 | 資生堂 | 10,673 | |
| 2 | コーセー | 2,891 | |
| 3 | 花王 ※ | 2,515 | |
| 4 | ポーラ・オルビスHD | 1,663 | |
| 5 | DHC | 874 |
※は化粧品関連の部門売上高。ランキングでは資生堂が首位を独走、コーセーと花王は順位が入れ替わり2位争いをしています。2022年は新型コロナによる影響も薄れ、売上高を大きく減少させるメーカーも多く、今後もランキングに変化が見られる可能性もあります。
2022年の大手化粧品メーカー3社の業績を見ますと、資生堂は前年比12.4%増の1兆673億円、コーセーは2.4%増の2,891億円、花王(化粧品事業)は同19.5%減の2,254億円でした。全体ではコロナ前の19年から約9割の回復となりました。
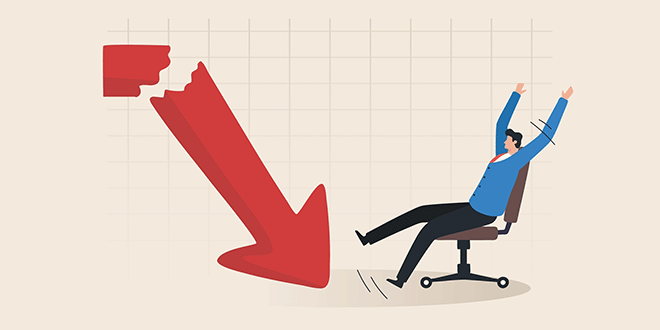
ここ数年、国内の化粧品市場は、旺盛な訪日外国人の需要を取り込めたことで、拡大傾向にありました。
なかでも、中国人観光客の消費は突出しており、国内の化粧品市場を下支えする存在でした。観光庁によると、コロナ禍前である2019年の化粧品購入単価は5万2千円と、他国に比べ断トツの消費力を見せていました。ところが、2020年以降はコロナ禍の影響にり状況は一変しています。
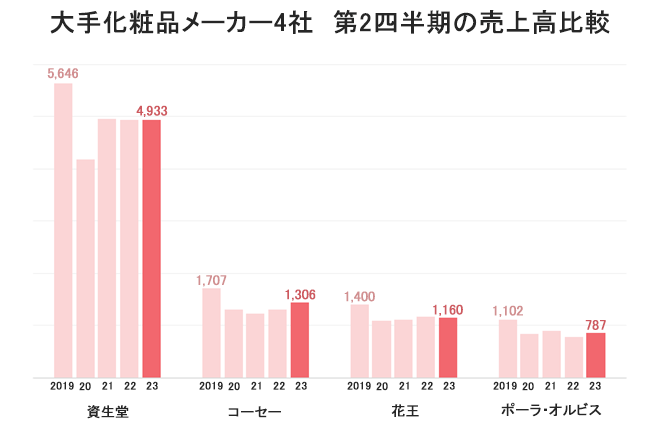
大手化粧品メーカー4社の第2四半期の売上高の比較(各社公表資料、グラフは業界動向サーチが作成)
上のグラフは、大手化粧品メーカー4社の2023年決算の中間業績の様子です。最新の動向を把握するために、中間決算を比較してみました。コロナ前である19年の水準と比較すると、資生堂は12.5%減、コーセーが15.5%減、花王17.3%減、ポーラ・オルビスHD22.1%減と、4社ともに2ケタ越えの大幅減少を記録しています。2021年には増加に転じたものの、その後は横ばいで推移している状態です。
近年の化粧品業界の状況をみますと、2020年は新型コロナによる世界的な感染拡大の影響で、訪日客は急減し期待のインバウンド需要も消滅、外出自粛やマスクの定化も加わり、化粧品需要は激減しました。
一方、2022年の春以降は口紅などのメイク用品の需要が伸びつつあります。なかでも、ドラッグストアを中心とした低価格帯の高機能商品が好調です。また、2022年10月以降は訪日外国人の受け入れが開始、2023年に入り百貨店での化粧品売上は回復傾向にあります。ただ、中国人観光客は戻っておらず、中国市場においても日本企業の高価格帯化粧品の消費は下振れています。
2022-2023年の化粧品業界の主なニュースを厳選してまとめました。直近の化粧品業界の動向を把握するのにご参考下さい。
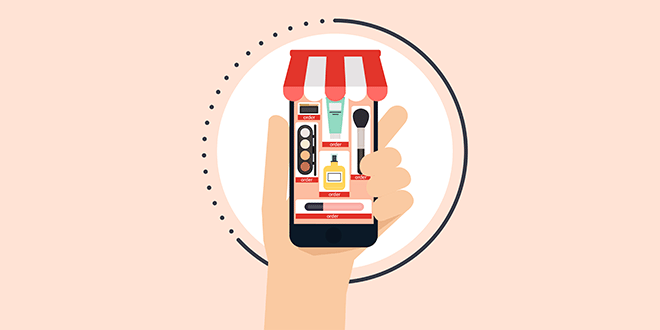
コロナ禍での化粧品業界では、対面やリアル店舗での販売という強みが活かせなくなったことを受け、自社プラットフォームを立ち上げるなど、デジタルシフトが加速しています。
資生堂は、デジタルマーケティングとEC拡大に注力し、2025年までにECの売上比率を40%に拡大することを掲げています。また、コロナ禍では三越伊勢丹HDのECサイト「meeco」にて、初の国内ライブコマースをスタート、オンライン上での「webカウンセリング」や、ECプラットフォーム「omise+」も立ち上げました。
資生堂は複数の会員サービスを一つに集約したアプリ「Beauty Key」をリリース
2022年9月には、複数の会員サービスを集約したアプリ「Beauty Key」をリリースしています。店舗やECなどの販売チャネルやブランドごとに分かれていた会員サービスを一つにまとめ、顧客の肌測定結果や購入履歴などを一元化し、商品開発や店頭での対応など顧客の満足度を向上させます。
コーセーでは、プラットフォームの確立とEC事業を加速させています。2020年3月には、オンラインサイト「Maison KOSÉ」でメイク画像や商品紹介を配信し、ECとの連携を高めています。また、2019年に銀座にオープンした体験型ストアでは、デジタル技術を活用した「デジタルカウンセリング」を提供するなど、オフラインとオンライン双方での顧客体験を追及しています
花王では、新型コロナによる影響で、消費者がオンライン購買へシフトすることを見込み、EC事業を強化しています。その結果、2020年の国内のEC売上比率は前年比20%越えと、大幅増を記録しました。
ポーラ・オルビスHDも同様にEC事業の強化を図っています。2023年には「EC売上比率を国内では30%」へと高める計画しています。
化粧品メーカー各社は、デジタル面の強化のみならず、時勢を捉えた「商品開発」にも注力しています。マスク着用の状態化が続いたなかでは、マスクにメイクがつきにくい商品や、マスクによる肌荒れを防ぐスキンケア商品など、外部環境の変化に適応した新製品の開発を迅速に行っています。
化粧品業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで化粧品市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | 資生堂 | 10,673 | ||
| 2 | コーセー | 2,891 | ||
| 3 | 花王 ※ | 2,515 | ||
| 4 | ポーラ・オルビスHD | 1,663 | ||
| 5 | DHC | 874 | ||
| 6 | マンダム | 670 | ||
| 7 | ノエビアHD | 611 | ||
| 8 | ファンケル ※ | 574 | ||
| 9 | 日本コルマー | 556 | ||
| 10 | 日本メナード化粧品 | 368 |
※花王は化粧品事業、ファンケルは化粧品関連事業の売上高です。シェアとは化粧品業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで化粧品市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ化粧品業界の詳細ランキングページにジャンプします。
化粧品業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
資生堂、コーセー、ポーラ・オルビスHD、DHC、マンダム、ノエビアHD、ファンケル、日本コルマー、日本メナード化粧品、新日本新薬、ナリス化粧品、ハーバー研究所、ハウス オブ ローゼ、日本色材工業研究所、アジュバンHD、総医研HD、アイビー化粧品、フォーシーズHDの計19社
化粧品業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。化粧品業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。