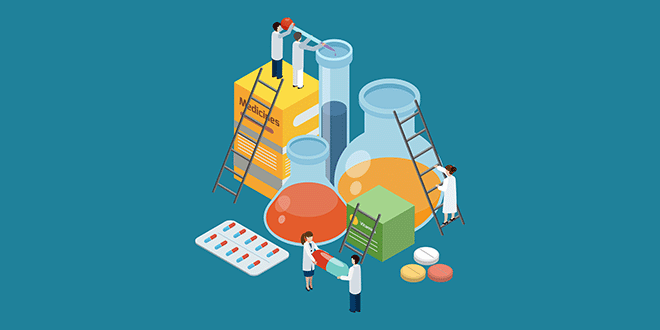
製薬業界の動向や現状、ランキングと課題や今後の展望などを解説しています。製薬業界の過去の業界規模の推移をはじめ、2022-2023年の動向と現状、業界が抱える課題と今後の見通しなどをご覧下さい。
業界規模
15.3兆円
成長率
8.3%
利益率
-1,042.9%
平均年収
809万円
製薬業界の過去の業界規模の推移を見ますと、中長期的に増加傾向にあります。
厚生労働省の「薬事工業生産動態統計年報(2023年12月公開)」によると、2022年の医薬品生産金額は前年比8.8%増の9兆9,819億円でした。前年から8,072億円が増加し大台の10兆円まで約2千億円となりました。
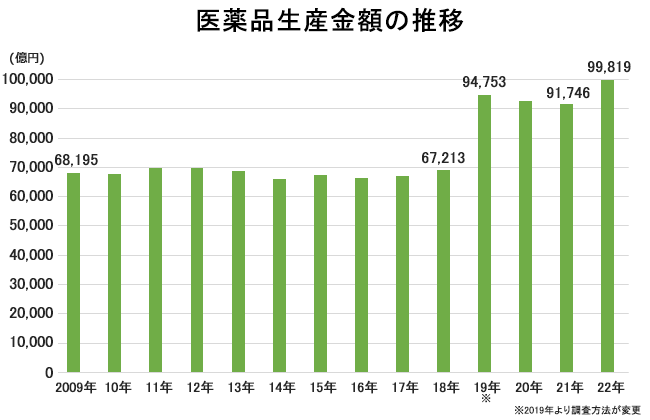
医薬品生産金額の推移(出所:厚生労働省、グラフは業界動向サーチが作成)
国内では少子高齢化によって医療費が増加傾向で、国民医療費は45兆359億円(2021年度)、国民医療費に占める薬局調剤医療費は7兆8千億円(2021年度)にも達しています。これにより国は薬価の引き下げを強化し、増加する薬剤費を抑えようと動いています。
国内の製薬業界市場は薬価改定による価格引き下が響き、縮小傾向にあります。新薬企業は収益の柱である主力薬の特許が切れたことで利益率が低下し、さらに膨大なコストと時間をかけた新薬も薬価低下の影響で収益を上げるのが難しい状況です。また、後発薬企業も開発コストは低いものの価格は新薬の半分以下になるため、薬価抑制は企業の利益に大きな影響を与えています。
こうした市況から、製薬メーカー各社は特許切れの薬剤事業や中核以外の事業売却、早期退職者を募るなど、コスト削減に乗り出しています。特許が切れた収益性の低い生活習慣病分野から、希少疾患薬などの高収益が見込める薬の開発にシフトしています。
国が後押ししている後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、2023年3月時点で使用率が80%までに増加しています。普及拡大で後発薬に参入する企業が増え、後発薬市場でも競争が激しくなっています。目標の80%を目前に市場の成長率は鈍化傾向にありましたが、ようやく目標の8割りに達しました。
近年の製薬業界を振り返りますと、2020年は新型コロナによる世界的な感染拡大で、海外の大手製薬会社のみならず、武田薬品工業などの国内企業も相次いでワクチンや治療薬の開発に取り組みました。2021年は主力製品が伸長し増収を記録しました。下期には感染再拡大による一部製品の出荷遅延や受診控えがあったもものの、影響は最小限で済んでいます。
2022年の製薬業界の動向をみますと、希少疾患やがん向けなどの主要製品や新製品が伸長しました。また、海外市場においては円安進行による恩恵も受けています。一方、毎年行われるようになった薬価改定の影響が響いており、各社厳しい状況が続きます。
※は製薬関連の部門売上高。2022年の製薬業界の売上高ランキングでは、武田薬品工業がトップを独走、次いでアステラス製薬、第一三共と中外製薬が3位争いをしています。武田薬品工業は2019年にアイルランドのシャイアーを買収し、メガファーマー入りを果たしています。
2023年3月決算の大手製薬5社の売上高は、武田薬品工業が前年比12.8%増、アステラス製薬は同17.2%増、第一三共は22.4%増、中外製薬は26.0%増、大塚HD(医療関連事業)は16.4%増でした。5社ともに2ケタ増を記録しています。
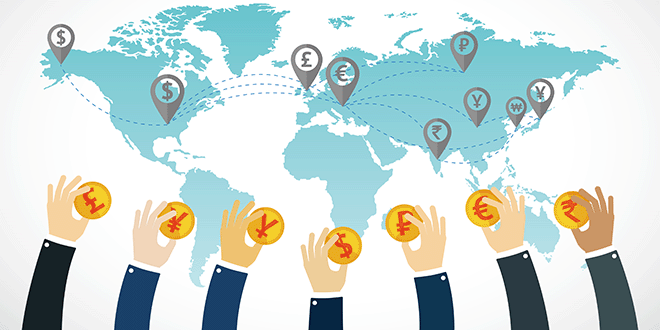
製薬業界が抱える課題は上記のとおりです。国内では医薬品の拡大が見込める一方で、国民一人当たりの医療費負担は年々増加しています。こうした状況から、薬価改定は従来の2年に1度から、毎年行われることとなりました。
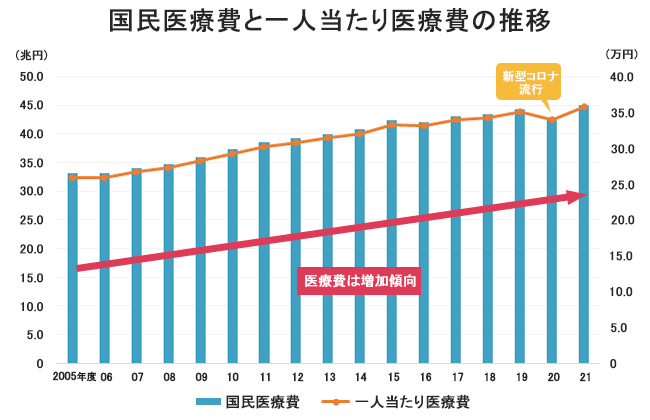
国民医療費と一人当たり医療費の推移(出所:厚生労働省より業界動向サーチが作成)
一方、新薬開発には膨大な費用と時間がかかるため、薬価の引き下げは企業収益を圧迫し、新薬開発を妨げる要因になります。
さらに、主力製品の特許切れも課題です。特許が切れた薬は低価格で後発薬企業が販売できます。政府は医療費削減のため、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及拡大を進めていますが、その一方で新薬メーカーの収益はさらに縮小します。
2023年6月、厚生労働省は後発薬普及に向け、特許切れの医薬品について自己負担の引き上げを検討しています。国や自治体の費用負担を削減しようと、さらなる後発医薬品の普及を目指しています。
また、後発薬製造メーカーにおいても、販売価格が新薬の5~4割以下となるなど、薄利多売の状態です。また、普及が進んだことで市場は頭打ちに近いことから、国内のジェネリック医薬品市場の成長は鈍化傾向にあり、後発薬メーカーにおいても収益の低下が課題となっています。

IQVIAによると、2024年から2028年の日本の医薬品市場の成長率は、年平均でマイナス2%~プラス1%と予測しています。薬価の引き下げが主な要因となっており、主要国の中では唯一日本のみがマイナス成長と予測されています。また、2028年までの国内市場は横ばいで推移し、国別の市場規模では3位を維持する見込みです。
新薬開発は年々難易度が高くなるうえに膨大な開発費を必要とする一方、薬価抑制策により国内市場での高収益維持が苦しくなっています。国内では市場の伸びが期待できないため、大手製薬会社は海外で事業を拡大、買収や提携に動いています。
現在、国内をメインとした企業は薬価引き下げの影響を大きく受けていますが、海外展開を積極的に行っている企業の業績は堅調です。今後は経済成長が著しい新興国でも医薬品市場の需要が見込めるため、いち早い海外需要の取り組みが必要です。
創薬の成功率は年々低下するなか、特許期間終了後は後発薬が普及するため、開発メーカーの収益はさらに縮小します。近年、新薬の開発にはAIやリアルワールドデータ(医療や健康のビッグデータ)を用いて、期間の短縮やコストの低減に取り組んでいます。今後も希少疾患薬、再生医療や遺伝子治療薬などの早期開発に向けて活用が進むでしょう。
日本の製薬メーカーは将来の成長のために、開発費の確保や新薬の特許取得、販路の拡大など、様々な対応が求められ、競争力が低い企業はさらに厳しい状況になるでしょう。画期的な新薬の開発能力や巨額の開発費が必要になるため、今後、大手・中堅メーカーを中心に資本力のある海外企業との提携が積極的に行われることが予想されます。
また、後発薬企業の間でも激しい競争が繰り広げられており、同じく再編の可能性が見えつつあります。
製薬業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで製薬市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | 武田薬品工業 | 40,274 | ||
| 2 | アステラス製薬 | 15,186 | ||
| 3 | 第一三共 | 12,784 | ||
| 4 | 中外製薬 | 12,599 | ||
| 5 | 大塚HD ※ | 11,378 | ||
| 6 | エーザイ | 7,444 | ||
| 7 | 興和 | 7,431 | ||
| 8 | 住友ファーマ | 5,555 | ||
| 9 | 小野薬品工業 | 4,471 | ||
| 10 | 塩野義製薬 | 4,266 |
※シェアとは製薬業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで製薬市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ製薬業界の詳細ランキングページにジャンプします。
製薬業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
武田薬品工業、アステラス製薬、第一三共、中外製
薬、大塚HD、エーザイ、興和、住友ファーマ、小野薬品工業、塩野義製薬、協和キリン、大正製薬HD、参天製薬、ロート製薬、東和薬品、サワイグループHD、日本新薬、ツムラ、久光製薬、杏林製薬、シミックHD、持田製薬、科研製薬、ゼリア新薬工業、キッセイ薬品工業、扶桑薬品工業、鳥居薬品、千寿製薬、ダイト、佐藤製薬などの計70社
製薬業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。製薬業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。