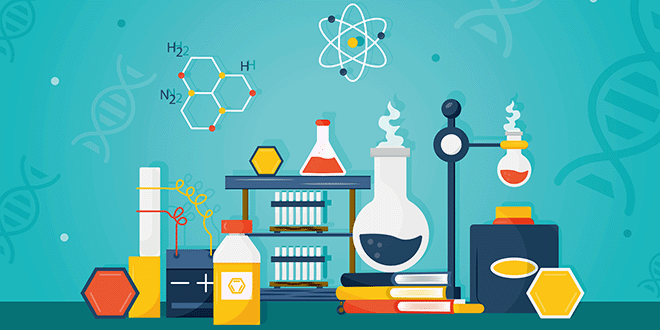
化学業界の動向や現状、ランキング&シェア、課題などを分析しています。化学業界の過去の業界規模の推移をはじめ、化学製造の売上高の推移グラフ、2021-2022年の動向と業界が抱える課題などを解説しています。
業界規模
35.1兆円
成長率
2.8%
利益率
6.5%
平均年収
657万円
化学業界の過去の業界規模の推移を見ますと、2018年から2020年まで減少傾向にありましたが、2021年には増加に転じています。
財務省の法人企業統計によると、2021年度の化学製造の売上高は、前年比11.3%増の44兆0,299億円でした。
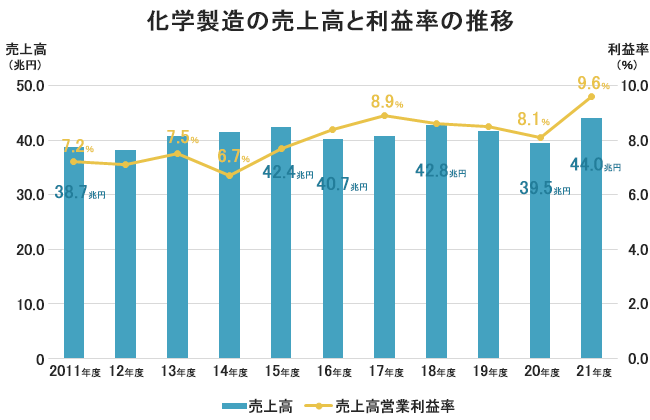
化学製造の売上高と利益率の推移(出所:財務省、グラフは業界動向サーチが作成)
化学製造の売上高を見ますと、年度によってばらつきがあるのが分かります。直近では2020年度は3年連続で減少し、2021年度は増加に転じています。全体としてはおおむね横ばいで推移しています。一方、売上高営業利益率は、中長期的に増加傾向です。
化学製品は少々複雑なのですが、原油由来の「ナフサ」を分解してエチレン、プロピレン、ブタジエンなどの「石油化学基礎製品(石化基礎製品)」をつくります。「石化基礎製品」からさらにポリエチレンやポリプロピレン、ブタジエンなどの「誘導品」に加工され、最終的にフィルムや樹脂成形品、アクリル繊維、合成ゴム、合成洗剤、ナイロン原料などの製品となります。
2021年は上記の「石油化学基礎製品」が好調に推移しました。世界的に供給不足となっていた半導体も回復傾向にあるかことから、半導体や自動車向けも業績アップに寄与しました。
2022年の化学業界では、引き続き半導体材料の需要は伸長した一方で、自動車用においては一部で需要の落込みが見られました。また、原材料価格が高騰しており、化学業界では価格転嫁を進めています。
一方で、原材料である原油や天然ガスの値動きは乱高下しました。原油先物市場は2022年半ばに直近高値を付けた後、減少傾向にあります。天然ガスは2022年は高値圏で増減を繰り返しており、不安定な値動きをしています。原材料の高騰は一旦、落ち着きを見せそうですが、世界的なインフレはいまだ収まっておらず、今後の原材料価格の上昇による採算性の低下に注意したいところです。
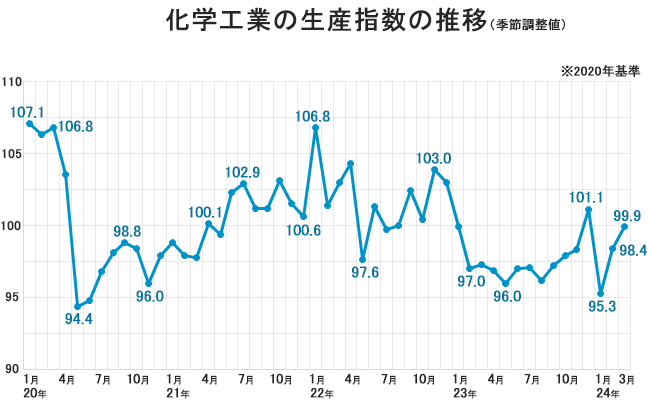
化学工業の生産指数の推移(出所:経済産業省、グラフは業界動向サーチが作成)
経済産業省の鉱工業指数によると、2025年11月の化学工業の生産指数は前年同月比1.5%増の95.4でした。2021年から2025年の推移を見ますと、増減は見られるものの全体では横ばいで推移していることが分かります。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | |
| 1 | 三菱ケミカルグループ | 39,769 | |
| 2 | 住友化学 | 27,653 | |
| 3 | 信越化学工業 | 20,744 | |
| 4 | 三井化学 | 16,126 | |
| 5 | 旭化成 ※ | 11,982 |
※は化学関連の部門売上高。2021-2022年の化学業界のランキングを見ますと、首位が三菱ケミカルグループ、2位が住友化学、3位が信越化学工業、三井化学、旭化成と続きます。いずれも売上高1兆円を超える巨大企業で、特に上位3社の売上高が大きいことが分かります。
2021-2022年は、化学メーカー上位5社中5社が増収を記録しました。業界全体でも増収となる企業が多く、好調な1年であったことが分かります。

続いて、化学業界が抱える課題について簡単に解説していきます。
原油などの化石燃料を原材料とする化学業界にとっては、世界的な「脱炭素」の動きは大きな逆風となっています。欧州や一部米国を中心に「脱炭素」の動きは広まっており、業界としても無視できない課題となっています。
また、原材料である原油や天然ガスの価格は近年、荒い値動きをしており、収益性の安定という観点からも問題があります。
こうした課題への対策として化学業界も動き出しています。汎用石化製品においては、原材料価格を自動的に製品の販売価格に転嫁させる「フォーミュラ制」が浸透しています。2021年12月には、レゾナック・HDが黒鉛電極にフォーミュラ制を導入するなど他分野への広がりも見せています。
一方で、機能製品分野ではいまだフォーミュラ制の導入があまり進んでいないため、この分野での制度の整備が課題となっています。
化学業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで化学市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | 三菱ケミカルグループ | 39,769 | ||
| 2 | 住友化学 | 27,653 | ||
| 3 | 信越化学工業 | 20,744 | ||
| 4 | 三井化学 | 16,126 | ||
| 5 | 旭化成 ※ | 11,982 | ||
| 6 | 日本ペイントHD | 9,982 | ||
| 7 | 日本酸素HD | 9,571 | ||
| 8 | 東ソー | 9,185 | ||
| 9 | 東レ ※ | 9,100 | ||
| 10 | エア・ウォーター | 8,886 |
※旭化成はマテリアル事業、東レは機能化成品事業の売上高です。シェアとは化学業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで化学市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ化学業界の詳細ランキングページにジャンプします。
化学業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
三菱ケミカルHD、住友化学、信越化学工業、三井化学、旭化成、日本酸素HD、エア・ウォーター、日本ペイントHD、日東電工、東ソー、東レ、DIC、宇部興産、三菱瓦斯化学、カネカ、クラレ、積水化学工業、JSR、昭和電工マテリアルズ、ダイセル、日亜化学工業、関西ペイント、デンカ、ADEKA、丸善石油化学、トクヤマ、日本ゼオン、日本触媒、東洋インキSCHD、ニフコなどの計191社
化学業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。化学業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。
化学 売上高ランキング(2021-22)
| 企業名 | 売上高 | ||
| 1 | 三菱ケミカルグループ | 39,769 | |
| 2 | 住友化学 | 27,653 | |
| 3 | 信越化学工業 | 20,744 | |
| 4 | 三井化学 | 16,126 | |
| 5 | 旭化成 | 11,982 |