
居酒屋業界の動向や現状、ランキング、トレンドなどを掲載しています。データは2022-2023年。対象企業の過去の業績を追うことで居酒屋業界全体の現状や動向、傾向を知ることができます。
業界規模
0.4兆円
成長率
-3.7%
利益率
-7.9%
平均年収
495万円
居酒屋業界の過去の業界規模の推移を見ますと、2020年、2021年と大きく落ち込みましたが、2022年には若干の増加に転じています。
居酒屋業界の過去の動向を見ますと、国内外の景気やライフスタイルの変化に左右されてきたことがわかります。世界的な欧州債務危機や新興国経済の成長鈍化などにより、景気の先行きが不透明な状況により、居酒屋業界も不振が続きました。
その後、円高の是正、株価の上昇など明るい兆しが見え始め、国内景気が回復基調へと転じました。こうした国内の経済動向を受け、居酒屋業界も徐々に回復基調へと好転。消費マインドも改善してきており、明るい兆しが見え始めました。
一方、2015年ごろから居酒屋業界は苦戦を強いられています。若年層のアルコール離れ、働き方改革による残業の減少、消費者の嗜好の多様化などが背景にあります。
そして、2020年から2021年の居酒屋業界は新型コロナウイルスの影響を直撃。感染対策としての休業や時短営業、さらにアルコールの提供停止などが響き、需要は縮小しました。不採算店の閉店や業態転換、ランチ営業を行うなど対策を開始しています。
2022年の居酒屋業界は昨年から業績は上向くも、全体ではコロナ前の水準には届かず苦戦を強いられた年でした。アルコール利用に比べ食事利用の回復が早いと踏まえ、居酒屋をレストランやテイクアウト業態へ転嫁、居酒屋業態ではフードメニューに注力するなど、収益基盤の強化に取り組みました。
一方、2023年3月には会食の人数制限の解除、同年5月には新型コロナウイルスが「5類」に移行したことで、居酒屋需要は回復傾向にあります。一方で食材や光熱費、輸送量などのコストが上昇するなど新たな課題に直面しています。
2022年(2022年3月決算)の大手居酒屋6社の売上高を見ますと、コロワイドは前年比21.2%増、ワタミは同21.2%増、モンテローザは89.0%増、大庄は24.0%増、魚力は1.2%減、DDホールディングスは66.8%増でした。2022年の居酒屋大手は約20~80%の増収を記録しています。
※はコロワイドMD事業の売上高。2021年の居酒屋業界売上高ランキングを見ますと、トップに位置しているのがコロワイドとワタミです。両社はコロナ禍で売上を大きく落し拮抗状態にあります。今後の状況では順位が入れ替わる可能性があります。
2022年の居酒屋業界の主要企業22社の売上高合計は、前年から一転して大幅なプラスとなりました。また、コロナ前である2019年の水準と比較すると、おおよそ8割の水準まで回復しています。また、最終利益が前年を上回ったのは22社中5社となっており、業界を取り巻く経営環境が厳しいことが分かります。
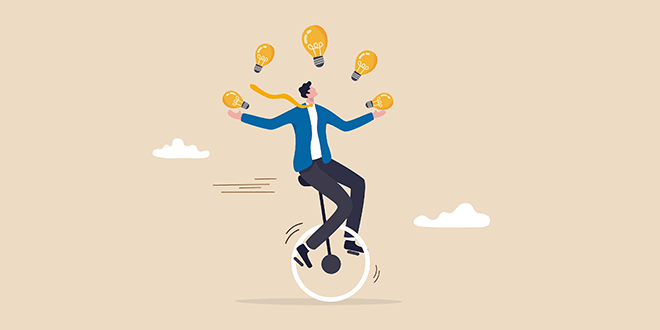
新型コロナウイルスが感染する以前から、居酒屋業界は若年層の「アルコール離れ」や「会社帰りの居酒屋需要の低下」など深刻な問題を抱えていました。
国税庁の酒類販売数量の推移を見ますと、酒類売上高は2001年ごろをピークに減少傾向。年代別にみた飲酒習慣率を見ても、50代が42.5%に対し、20代は4.7%(厚生労働省2010年男性データ)とかなり低い傾向に。近年の若者のアルコール離れは顕著となっており、居酒屋業界にとっては深刻な問題になっています。
また、近年ではファミレスやラーメン店でのアルコール類の提供など他業種の居酒屋部門の参入が目立ちます。他業種による「ちょい飲み」需要の競争が激しくなり、各社の収益力の低下につながってきました。
加えて働き方改革による残業の減少など社会的な変化も居酒屋業界にとっては逆風です。以前のように「仕事帰りにちょっと一杯」といった習慣も薄れ、「家飲み」が流行るなど消費者のライフスタイルの変化もみられます。
各社は不採算店を業態転換するなど様々な試みを行っていますが、本格的な業績の回復には至っていません。
このような状況の中で新型コロナウイルスが拡大。ワタミは65店舗の閉店と新業態の焼肉店や唐揚げ専門店を展開することを発表。都心を中心に展開していたSANKO MAERKTING FOODSは郊外の居酒屋にシフトしています。また、鳥貴族ではテイクアウトやチキンバーガー専門店を開始、その他、ランチ営業を始めるチェーン店など、各社様々な取り組みを行っています。
居酒屋業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで居酒屋市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | コロワイド ※ | 779 | ||
| 2 | ワタミ | 779 | ||
| 3 | モンテローザ | 618 | ||
| 4 | 大庄 | 357 | ||
| 5 | 魚力 | 337 | ||
| 6 | DDホールディングス | 322 | ||
| 7 | SFPホールディングス | 229 | ||
| 8 | 鳥貴族HD | 202 | ||
| 9 | チムニー | 201 | ||
| 10 | エー・ピーHD | 171 |
※コロワイドはコロワイドMD事業の売上高です。シェアとは居酒屋業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで居酒屋市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ居酒屋業界の詳細ランキングページにジャンプします。
居酒屋業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
コロワイド、ワタミ、モンテローザ、大庄、魚力、DDホールディングス、SFPホールディングス、鳥貴族HD、チムニー、エー・ピーHD、ヨシックスHD、ヴィア・HD、テンアライド、ジェイグループHD、ハブ、SANKOMARKETINGFOODS、一家HD、NATTYSWANKY、ユナイテッド&コレクティブ、マルシェ、海帆、かんなん丸の計22社
居酒屋業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。居酒屋業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。