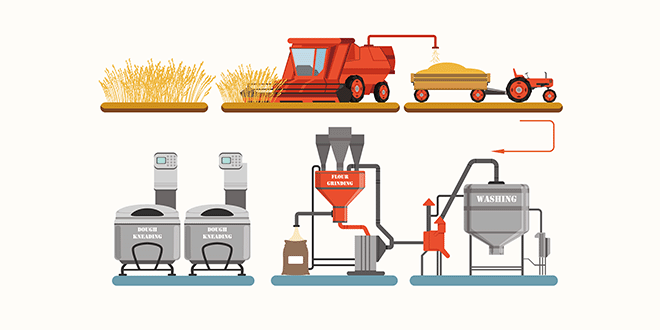
製粉業界の動向や現状、ランキング、売上高シェアなどを掲載しています。データは2022-2023年。過去の製粉業界の市場規模の推移をはじめ、小麦消費量の推移や最近の消費者のトレンド、製粉大手3社の海外事業の現状、製粉業界の今後の動向などをご紹介しています。
業界規模
1.6兆円
成長率
5.3%
利益率
2.9%
平均年収
700万円
製粉業界の過去の業界規模の推移を見ますと、直近の2022年は大幅に増加しています。
下のグラフは小麦の国内消費仕向量の推移をあらわしたものです。
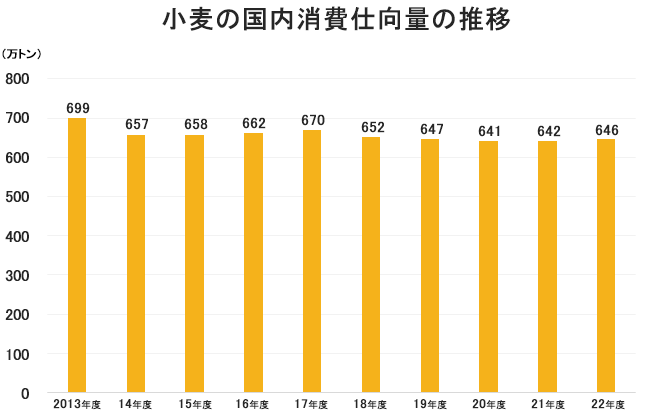
小麦の国内消費仕向量の推移(出所:農林水産省、グラフは業界動向サーチが作成)
農林水産省の食糧需給(2023年8月7日公表)によると、2022年度の小麦の消費仕向量(国内で小麦粉に使用される小麦の量)は、前年度比0.7%増の646.9万トンとなりました。
2022-2023年の製粉業界の動向を見ますと、国内では経済活動の回復が見られたことで、業務用製粉の需要は昨年に続き、堅調に推移しています。家庭用は縮小傾向にあった昨年から一転して、持ち直しの動きが見られています。海外市場においては、主に米国での業績が好調に推移、小麦の相場上昇や為替なども業績に貢献することとなりました。
2021-2023年に入り、大手製粉会社は相次いで値上げを実施しています。小麦の価格高騰に加え、円安や燃料費高などの影響を大きく受けており、コスト上昇分を商品価格に転嫁し始めています。全体的には後追いの印象を受けますが、価格転嫁が進めば収益性の改善も期待できます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | |
| 1 | 日清製粉グループ本社 | 7,986 | |
| 2 | ニップン | 3,655 | |
| 3 | 昭和産業 | 3,350 | |
| 4 | 日東富士製粉 | 695 | |
| 5 | 日本食品化工 | 646 |
製粉業界の2022-2023年の売上高ランキングを見ますと、日清製粉Gが大きくリード、ニップン、昭和産業と続きます。
日清製粉G本社は製粉の国内最大手で、北米でも30年ほど前から展開しています。ニップンは国内2位の製粉会社で、小麦粉やふすま、そば粉などを展開しています。昭和産業は小麦粉やプレミックスなどを展開しており、家庭用ではホットケーキミックスなどを展開していいます。

大手製粉会社では海外事業を成長事業の一つと位置付けており、海外における製粉会社の買収および小麦粉やプレミックスの新工場の建設を進めています。
業界首位の日清製粉グループ本社は、すでに小麦粉の生産能力は海外が60%を占めており、国内の1.5倍の規模に拡大しています。2012年の米国進出をきっかけにニュージーランドの製粉事業やタイの製粉会社を買収。2018年には豪州最大の製粉会社「アライド・ピナクル」の買収で、豪州市場への本格参入を果たしています。
業界2位の日本製粉は、ASEAN地域におけるプレミックス需要の高まりを受け、中国とタイにプレミックス工場を増設、海外での生産能力の増強を図っています。その他、米国やインドネシアにも進出しており、今後も海外事業比率を伸ばす意向です。
同3位の昭和産業も同様にASEAN地域でのプレミックスの製造を強化しており、2018年にはベトナムに新会社を設立。また、2019年11月には台湾の「大成集団」との合弁事業を発表し、事業領域の拡大を進めています。
国内市場は少子高齢化に伴う需要の減少で、今後大きな消費が見込めないことが予想されています。こうした市況により、製粉大手3社は成長著しいASEAN地域や消費の拡大が見込める海外での事業拡大を加速させています。
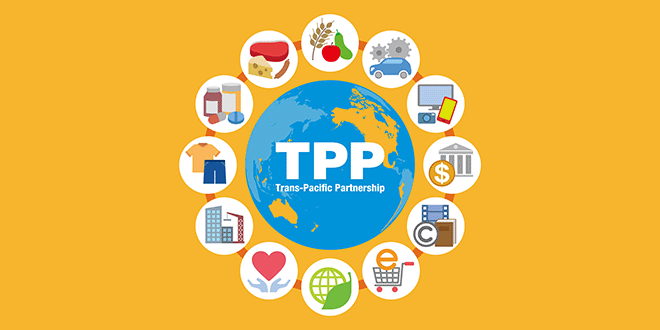
製粉業界は、原材料である小麦の価格に影響を受けやすい業界です。
日本で消費される小麦は約9割が輸入頼みです。政府が一括で買い入れた小麦を国内の製粉会社が買取る「政府売渡制度」が設けられており、輸入小麦の価格は政府によって決められています
また、小麦の価格は関税や為替、天候不順、輸送コスト、新興国の食生活の変化など様々な要因が反映されており、小麦粉価格は下落や上昇を繰り返すなど不安定な相場が続いています。さらに、2022年2月のロシア・ウクライナ危機により、小麦の国際価格が高水準で推移しています。このような市況は製粉会社の業績に大きな影響を与えています。
国際貿易関係では2018年の「TPP11協定」、2019年の「日EU・EPA協定」や日米貿易協定が発足し、小麦や小麦粉製品の二次加工製品の関税引下げが進んでいます。
そうした中、製粉業界では貿易協定をリスク要因の一つとして認識しています。関税引き下げによる輸入品の二次加工品(パスタやクッキー等)の需要拡大により、国内の小麦粉需要は減退し、製粉業界の規模が縮小する恐れがあります。
今後、世界的な人口の増加、異常気象による穀物の収穫減など世界の穀物相場の高騰と食料争奪のリスクが懸念されます。また、ビジネス環境が大きく変化することで業界内での競争激化、さらなる事業拡大を求め、業界再編や事業提携など大きな動きが起きる可能性もあります。
製粉業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで製粉市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | 日清製粉グループ本社 | 7,986 | ||
| 2 | ニップン | 3,655 | ||
| 3 | 昭和産業 | 3,350 | ||
| 4 | 日東富士製粉 | 695 | ||
| 5 | 日本食品化工 | 646 | ||
| 6 | 鳥越製粉 | 244 |
※シェアとは製粉業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで製粉市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ製粉業界の詳細ランキングページにジャンプします。
製粉業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
日清製粉グループ本社、ニップン、昭和産業、日東富士製粉、日本食品化工、鳥越製粉の計6社
製粉業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。製粉業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。