
総合商社業界の動向や現状、ランキングなどを研究してます。データは2022-2023年。2022年-2023年の資源価格と商社の業績の比較、非資源化を進める各社のDXへの取り組みなどを解説してます。
業界規模
79.0兆円
成長率
13.7%
利益率
5.3%
平均年収
1530万円
総合商社業界の過去の業界規模の推移を見ますと、直近の2021、2022年は大幅に増加しています。
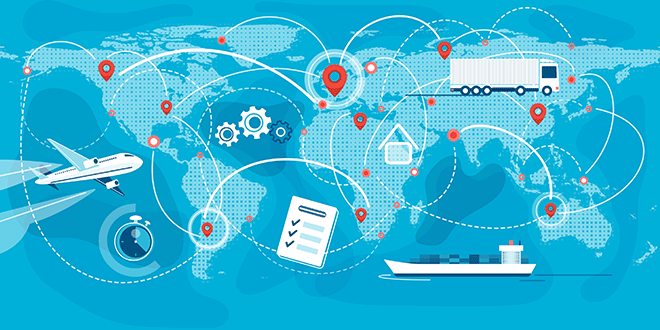
総合商社とは、「トレーディング」や「事業投資」を主に行う会社です。総合商社の仕事内容は分かりにくいものですが、その変遷をたどっていくことできちんと理解できるようになります。
「トレーディング」とは、原産者とメーカーの結びつきを行う仕事です。トレーディングは従来からある商社の仕事で、原産者とメーカーの仲介のような役割を果たします。
メーカーは商品や製品を製造するのに様々な原料が必要になります。しかしながら、それを直接買い付けるネットワークやノウハウを持ち合わせていません。そこで膨大なネットワークを持った総合商社が中に入り、原産者とメーカーを結びつけます。
一方で、1990年代のインターネットの普及に伴い、メーカーが独自に生産者を探して買い付けるいわゆる「商社外し」が発生し、「商社不要論」が叫ばれるようになりました。これに危機感を持った総合商社は、原産者、メーカー、小売(いわゆる川上から川下まで)に直接出資をしてバリューチェーンそのものを押さえる動きが生まれました。これが、「事業投資」の始まりです。
2000年代に入ると総合商社は、従来の「トレーディング」から「事業投資」へと本格的にシフトし始めます。こうした変遷の結果、現在の総合商社は「事業投資」が収益の柱となっています。総合商社は、様々な分野で持分法適用会社や連結子会社を所有しており(例:三菱商事は約1,700社の連結会社)、「持分利益」や「配当」などの形で利益を得るモデルが定着しています
ちなみに、総合商社はセグメントの中で「資源」の影響を受けやすい点が特徴です。したがって、総合商社の業績は資源価格に左右される場合が多く、資源価格が下落しているときは業績が悪化し、資源価格が上昇しているときは業績が良い傾向にあります。
下のグラフは、主な総合商社業界の過去10年間の純利益の推移を示したものです。
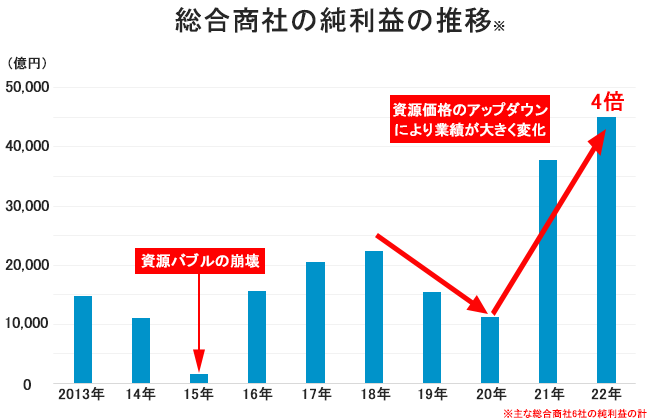
総合商社の純利益の推移(出所:各社決算資料、グラフは業界動向サーチが作成)
グラフによると、直近の2018年から2020年までは減少傾向にありましたが、2021年と2022年に大幅に増加しています。2022年の総合商社6社の純利益の合計は4.5兆円でした。20年比で約4倍の驚異的な増加を記録しています。
近年の総合商社業界は好調な業績を残しています。世界的な金融緩和や渡航制限による労働者不足、経済再開期待などを背景に資源価格が上昇しました。とくに、2021年後半から2022年にかけては原油をはじめ、銅やLNGなどの資源価格が高騰。世界的なサプライチェーンも回復傾向にあり、2023年決算の総合商社は7社が過去最高益を記録しています。
2022-2023年の総合商社業界の純利益ランキングによると、首位が三菱商事で2位が三井物産、3位が伊藤忠商事でした。
2022-2023年は5社が増収、4社が増益となりました。世界的な資源価格の高騰が業績を押し上げました。とくに、三井物産や三菱商事、丸紅など資源・エネルギー関連が強い商社が業績を伸ばしています。
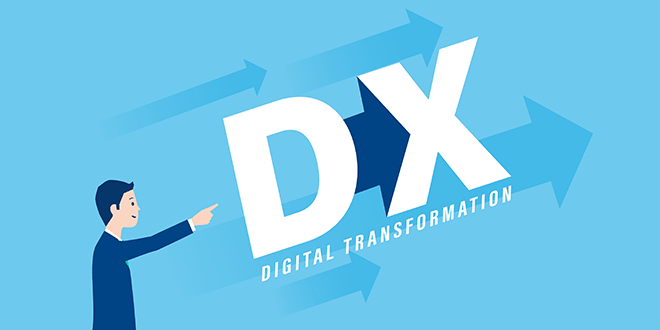
近年の総合商社は、過去の資源バブル崩壊などの経験から『非資源分野』を強化しています。2021-2022年は資源高の恩恵をフルに受けた一年でしたが、過去には資源安の影響により業績を悪化させた年もありました。このように資源価格の影響は総合商社にとって大きく、資源価格に振り回されない安定した経営を各社目指しています。
非資源分野の取り組みとしては、各社強みを生かした事業再編を行っていますが、全社的に取り組んでいるテーマはDX(デジタルトランスフォーメーション)です。
三菱商事は、DXによる食品流通の最適化を模索しています。
三菱商事が目指すDX
三菱商事は、AIによる食品需要の予測をメーカー、食品卸、小売りが共有する仕組みを考えました。AIによる需要予測をバリューチェーンで共有することで、在庫の最適化を図り、作り過ぎによる食品ロスの減少を目指します。
伊藤忠商事は、バリューチェーンの最適化に加え、消費者接点の高度化を意識したDXを推進していきます。ファミリーマートにおけるサイネージ広告の設置や「ファミペイ」アプリの拡大、小売分野ではAIカメラを活用した顧客行動分析などを行います。
人口が減少する日本において、「生産性の向上」や「新しいビジネスの構築」は待ったなしの課題です。今後、あらゆる産業でDX化は進んでいくでしょう。バリューチェーン全体を押さえている総合商社にとって、DX導入のインパクトは非常に大きいものです。総合商社のこうした取り組みは、日本の産業全体のDXを加速させる可能性を秘めています。
総合商社業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで総合商社市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | 三菱商事 | 215,719 | ||
| 2 | 三井物産 | 143,064 | ||
| 3 | 伊藤忠商事 | 139,456 | ||
| 4 | 豊田通商 | 98,485 | ||
| 5 | 丸紅 | 91,904 | ||
| 6 | 住友商事 | 68,178 | ||
| 7 | 双日 | 24,798 | ||
| 8 | 兼松 | 9,114 |
※シェアとは総合商社業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで総合商社市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ総合商社業界の詳細ランキングページにジャンプします。
総合商社業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、豊田通商、丸紅、住友商事、双日、兼松の計8社
総合商社業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。総合商社業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。