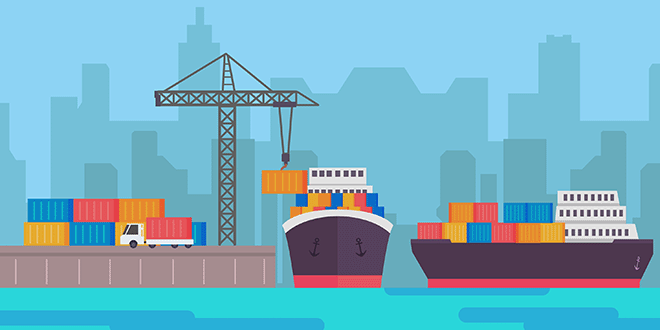
海運業界の動向や現状、ランキング&シェアなどを分析しています。海運業界の過去の市場規模の推移をはじめ、海運上位3社の売上高の推移、業界を取り巻く規制の動向や今後に向けた各社の取り組みなどを解説しています。
業界規模
5.9兆円
成長率
14.6%
利益率
16.2%
平均年収
921万円
海運業界の過去の業界規模の推移を見ますと、2021年、2022年と大幅に増加しています。
下のグラフは海運業界の主な企業3社の売上高の推移を示しています。
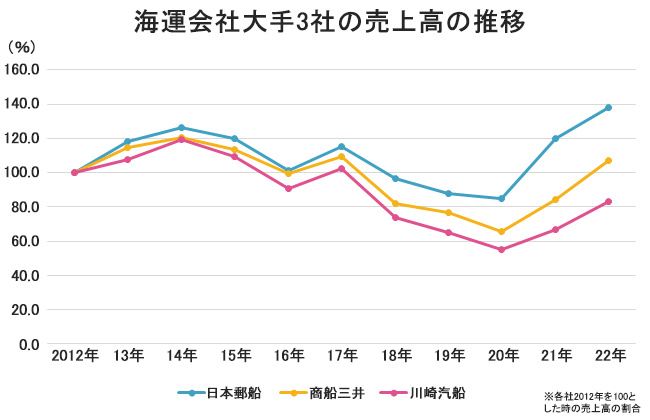
海運大手3社の売上高の推移(各社公表資料、グラフは業界動向サーチが作成)
グラフを見ますと、海運大手3社は売上の差はあるものの、ほぼ同様の動きをしています。ここ数年の売上高は減少が続き厳しい状況で、21年3月期は軒並み減収でした。一方、22年3月期には3社ともに大幅増加、2023年3月期も2年連続の大幅増収となりました。
2022-2023年の海運業界の動向を見ますと、大手海運3社は昨年に引き続き大幅増収、過去最高益を更新しています。上期は自動車の減産が解消され自動車輸送台数が増加、加えて港湾の混雑により物流が混乱するなど供給が制約されたことで、コンテナ船の運賃が高騰しました。
一方、下期に入り欧米を中心とした利上げによる景気後退懸念から、消費財の在庫が積上がり需要が減退、港湾の混乱も解消したことで運賃が下落しました。上期と下期で状況が変化したものの、上期が好調に推移したことで全体では好調な業績となりました。
一方、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻を受け、日本郵船がロシアの自動車陸送事業の撤退を検討しています。また、世界的なインフレ進行による景気後退リスクなど、海運業界の事業環境は不確実性が高まっています。
海上輸送を行う海運業界は「内航海運(国内)」と「外航海軍(海外)」に分かれます。輸送品の種類に応じて様々な輸送船が存在し、コンテナ輸送の「コンテナ船」、穀物や鉱石などを梱包せずにそのまま輸送する「バラ積み船」、液体輸送の「タンカー」、自動車に特化した「自動車船」、化学薬品用の「ケミカルタンカー」などがあります。
海運会社は「内航、外航、船の種類」によって得意不得意があり、各社棲み分けがなされています。とくに国内の大手海運会社の収益源は、不定期船(バラ積み船、自動車船、LNG千、油送船)です。また、一部の海運会社は一般消費者向けに、フェリーなど旅客船を扱っています。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | |
| 1 | 日本郵船 | 26,160 | |
| 2 | 商船三井 | 16,119 | |
| 3 | 川崎汽船 | 9,426 | |
| 4 | NSユナイテッド海運 | 2,508 | |
| 5 | 飯野海運 | 1,413 |
2022年の海運業界の売上高ランキングを見ますと、トップが日本郵船、2位が商船三井、川崎汽船、NSユナイテッド海運、飯野海運と続きます。売上高では日本郵船が独走しており、2位以下を大きく引き離しています。
日本郵船と商船三井、川崎汽船の3社はコンテナ事業を統合し「ONE」を設立、2018年よりサービスを開始しています。
2022-2023年の海運業界の業績を見ますと、日本郵船が前年比14.7%増、商船三井が同28.0%増、川崎汽船が21.0%増となり、大手3社ともに前年から大幅な増収を記録しました。また、各社の純利益も過去最高となり、日本郵船においては1兆円超えとなりました。
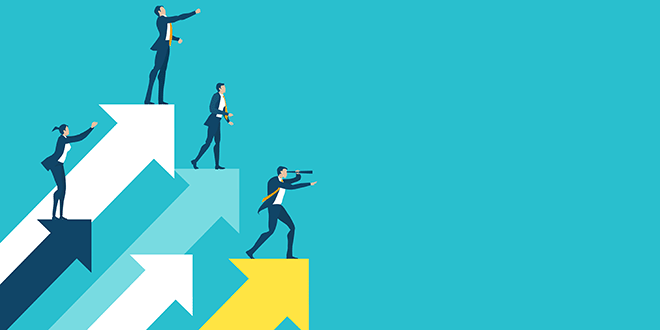
コンテナ船市場のシェア争いが世界的に激化したことを受け、国内の海運大手3社はコンテナ事業の統合で新会社「ONE社」を設立し、シェア拡大によるコンテナ船事業の収益確保に努めています。さらに、各社はそれぞれに市況の変動に左右されにくい事業に注力し始めています。
業界トップの日本郵船は、ボラティリティへの体制強化と収益力の向上を図ります。運賃安定型事業として総合物流を強化し、海上や航空ともに取扱量を拡大しています。また、DXではブロックチェーンによるラットフォームの構築で、貿易情報を一元化し手続きの利便性向上を図ります。
日本郵船は「アンモニア燃料国産エンジン搭載船舶」の社会実装に向けた実証事業を開始
さらに同社は、曳船事業において国内最大級の強みを活かし「アンモニア燃料タグボート」の建造や「洋上風力関連事業」にも注力しています。特に日本郵船含む5社共同の「アンモニア燃料タグボート」では国産エンジンを搭載し、2024年には内航船を造船、外航船は2026年度をメドに就航を目指します。
商船三井では、海洋資源開発や、再エネを含む洋上でのエネルギー生産の分野を積極的に展開していきます。主に特定の場所に浮かべて活用する「浮体式LNG貯蔵再ガス化設備」や「洋上風力」を強化します。また、地域戦略では液体輸送の日本コンセプトと新会社を設立し、化学品需要を見込めるインドや中国での営業活動を行います。
川崎汽船は「ドライバルク、自動車船、エネルギー資源、物流」の4事業を強化します。収益の向上を見据え、2020年8月には非コア事業の「米ターミナル子会社」を売却、さらに新たな事業領域として「洋上風力支援船」や「新エネルギー輸送需要(アンモニア、水素、CO2等)」にも注力しています。
新型コロナの影響を受けた2020年は、海運大手3社がそろって減収となりました。2021年、2022年は状況が一転し、コンテナ船の運賃の高騰により大幅増収、純利益も2年連続で過去最高を更新しています。一方、ウクライナ危機や景気後退が懸念材料となっており、世界貿易に依存する海運業界にとっては予断を許さない状況です。各社いずれも変化の厳しい海運市場に対処すべく、様々な事業を模索しています。
海運業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで海運市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | 日本郵船 | 26,160 | ||
| 2 | 商船三井 | 16,119 | ||
| 3 | 川崎汽船 | 9,426 | ||
| 4 | NSユナイテッド海運 | 2,508 | ||
| 5 | 飯野海運 | 1,413 | ||
| 6 | ENEOSオーシャン | 675 | ||
| 7 | 明治海運 | 580 | ||
| 8 | 新日本海フェリー | 553 | ||
| 9 | 栗林商船 | 498 | ||
| 10 | 乾汽船 | 442 |
※シェアとは海運業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで海運市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ海運業界の詳細ランキングページにジャンプします。
海運業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
日本郵船、商船三井、川崎汽船、NSユナイテッド海運、飯野海運、ENEOSオーシャン、明治海運、新日本海フェリー、栗林商船、乾汽船、共栄タンカー、東海汽船、東京汽船、佐渡汽船、東海運、玉井商船の計16社
海運業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。海運業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。
海運 売上高ランキング(2022-23)
| 企業名 | 売上高 | ||
| 1 | 日本郵船 | 26,160 | |
| 2 | 商船三井 | 16,119 | |
| 3 | 川崎汽船 | 9,426 | |
| 4 | NSユナイテッド海運 | 2,508 | |
| 5 | 飯野海運 | 1,413 |