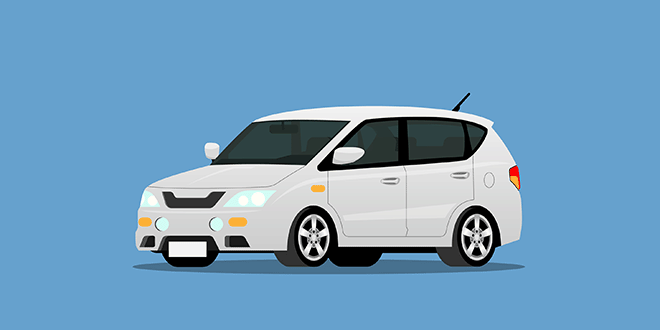
自動車業界の業界レポート。動向や現状、ランキングなどを分析しています。世界の自動車販売台数の推移やメーカー別ランキング、市場規模の推移、国内外の現状や動向、2022年の業界ニュース、最近のトレンドである「CASE」の状況と各社の取り組みなどを詳しく解説しています。
業界規模
77.1兆円
成長率
6.6%
利益率
3.4%
平均年収
749万円
自動車業界の過去の業界規模の推移を見ますと、直近の2年は増加傾向にあります。
OICA(国際自動車工業会)によると、2022年の世界の自動車販売台数は前年比1.4%減の8,162万台、生産台数は6.0%増の8,501万台でした。2022年は前年から横ばいで推移しています。
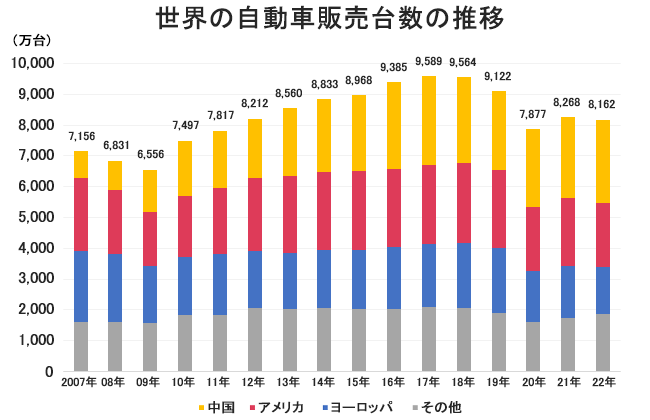
中国、米国、欧州と世界の自動車販売の推移(出所:OICA、グラフは業界動向サーチが作成)
上のグラフは世界の自動車販売台数と国・エリア別の推移をあらわしたものです。2022年現在、世界の自動車業界は中国が最大の市場で、米国、欧州と続きます。2022年は中国が販売台数で前年比2.1%増の2,686万台、米国が5.1%減の2,088万台、欧州は10.7%減の1,508万台でした。
過去数年の動向を見ますと、中国が世界の自動車市場を牽引してきたことが分かります。米国、欧州市場は横ばいで推移しているものの、その伸びは鈍化しています。直近の動向では、中国市場は鈍化の兆しを見せており、米国が再び勢いを増してきました。
2022年の自動車販売では東南アジアが前年比17.6%増、インドが25.7%増と非常に高い伸びを記録しました。また、販売台数は少ないもののベトナムやフィリピンも25~26%増加しています。今後は成長余力のある東南アジアやインドなど新興国市場をいかに取り込めるかがカギとなりそうです。
| 順位 | 企業名 | 販売台数(万台) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 1,048 | |
| 2 | フォルクスワーゲン | 826 | |
| 3 | 現代自動車 | 684 | |
| 4 | ルノー・日産・三菱 | 615 | |
| 5 | ステランティス | 600 | |
| 6 | ゼネラル・モーターズ | 593 | |
| 7 | フォード・モーター | 423 | |
| 8 | ホンダ | 377 | |
| 9 | スズキ | 296 | |
| 10 | 上海汽車集団 | 278 | - |
続いて世界のメーカー別販売台数を見ていきましょう。2022年の世界自動車販売台数ランキングでは、首位がトヨタ自動車で1,048万台、2位がフォルクスワーゲンで826万台、3位が現代自動車で684万台、ルノー・日産・三菱が615万台となっています。
ランキングでは、トヨタとフォルクスワーゲン、ルノー・日産の3社が販売台数で首位争いし三強状態にありました。一方で2022年はルノー・日産・三菱が4位に転落、3位に現代自動車が浮上しています。
2022年は全体では昨年よりも販売数が減少しており、メーカーにより優勝劣敗が進んでします。ランキング上位では首位のトヨタ自動車が1千万台をキープし、フォルクスワーゲンとの差を広げています。
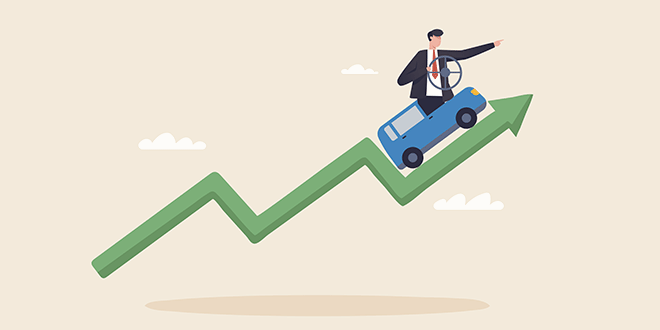
OICAによると、2022年の日本国内の自動車販売台数は前年比5.6%減の419万台でした。乗用車は前年比6.2%減、商用車は1.6%減でした。日本の自動車販売台数は4年連続の減少となります。
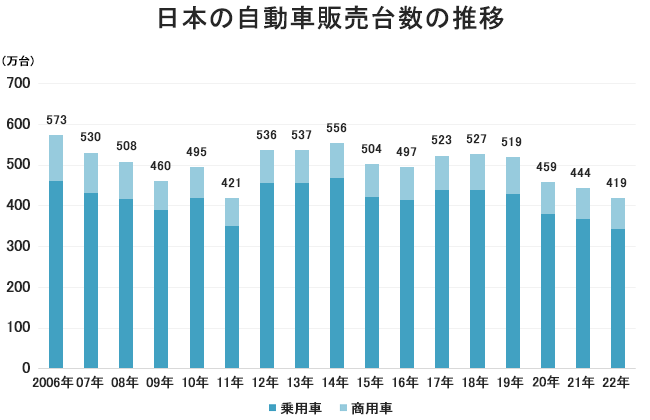
日本の自動車販売台数の推移(出所:OICA、グラフは業界動向サーチが作成)
日本の自動車販売台数の推移をみますと、増減を繰り返しながら中長期的には減少傾向にあります。2021年は世界の自動車市場が回復を見せる中、日本は減少となりました。2022年も引き続き減少しており、国内での新車販売は頭打ちが鮮明となっています。2022年現在の販売台数は1990年代の3分の2ほどと落ち込んでいます。
車種別にここ数年の状況を見ますと、2021年はコンパクトカーなど小型車の販売が好調でした。ブランド別販売ランキングでは、2020年まで好調だった軽自動車がランクダウンし、コンパクトカーなどの小型車がランクアップしています。近年、軽自動車は価格が上昇傾向にあり、ここ10年で5割近く上昇しています。従来、リーズナブルとされていた軽自動車に割高感が見られることから、軽自動車から小型車へのシフトが見られました。
一方、2022年は再びN-BOXが首位に返り咲いています。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会の発表によると、2022年のブランド別販売台数は、軽自動車の「N-BOX」が20万2,197台、乗用車は「ヤリス」の16万8,557台となりました。
近年、日本国内での自動車販売が振るいません。日本国内の販売台数が振るわない原因は様々ありますが、主に短期的なものと長期的なものがあります。短期的な原因は自動車部品の不足による販売減です。新型コロナやウクライナ危機などの影響により、自動車部品の供給が滞っています。車種にも寄りますが、注文から納車まで半年を超えるクルマもあり、注文は受けているものの販売にカウントできない受注残が積み上がっています。
長期的な要因としては自動車価格の上昇です。近年は国民の所得が変わらないにもかかわらず、クルマの価格は上昇しています。最近の自動車は安全性能や環境性能の向上に加えて、資材価格も高騰しており、従来価格よりも20~30万円ほど高い設定となっています。以前は割安と言われていた軽自動車の価格も10年で5割も増加するなど大幅に上昇しているため、買い控えをする消費者が増えています。
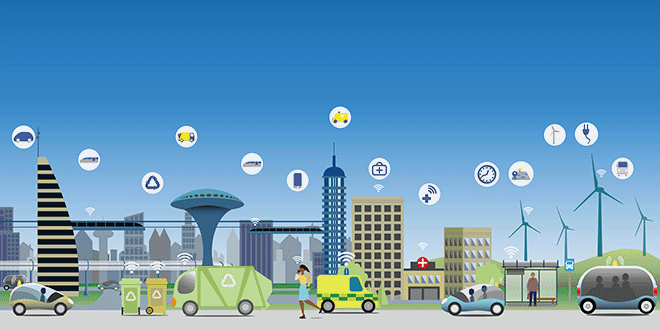
現在の自動車業界は「100年に1度の大変革時代」とも言われています。最近では世界各国の自動車メーカーで「CASE」という言葉がトレンドとなっており、今後の自動車業界の未来を語るうえで欠かせない言葉となっています。
「CASE」とはConneted Autonomous Shared Electricの略で「コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化」を意味しています。
「コネクテッド」とは簡単に言えば、自動車がネットに常時接続することです。クルマがネットに接続することで、現在位置の把握や配送の効率化、最適なルート提案、事故発生時の通報など様々なことが可能になります。また、自動運転ではクルマが今どこにいるかを把握する必要があるため、コネクテッドの技術は欠かせないものとなります。
現在の自動車業界はこれら4つの技術と概念が同時進行で進んでおり、業界を取り巻く環境が大きく変わろうとしています。
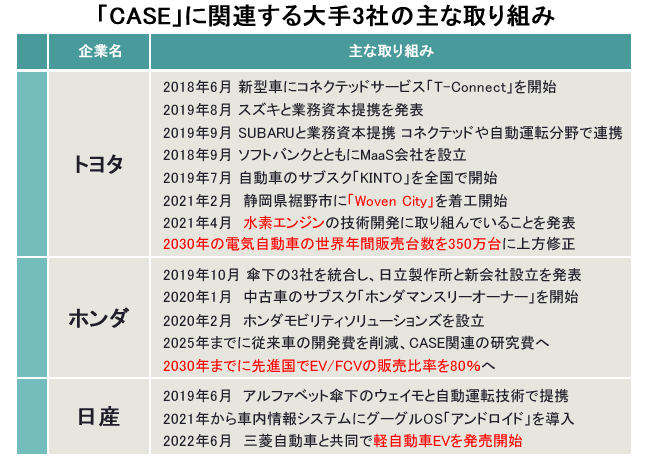
トヨタ自動車は従来のモノづくり中心の会社からモビリティに関わる「モビリティカンパニー」へのフルモデルチェンジを掲げています。さらに、クルマの枠にとらわれずクルマを含めた社会全体という大きな視点に立った「コネクテッド・シティ(ウーブン・シティ)」の建設を2021年に静岡県裾野市で行うと発表しました。2025年ごろまでの工事を経て、段階的にオープンするものとみられています。トヨタ自動車はこうした「CASE」関連の試験開発費に現在は4割、将来的には5割を投入するとしています。
ホンダも「モビリティを取り巻く環境は大きな変革期にある」とし、CASE対応の動きを強めています。2019年10月には傘下の自動車部品メーカーを統合させ、日立製作所と新会社設立を発表しました。また、2022年以内に東京都心部で「レベル4自動運転」の実証実験を実施することを発表しています。
近年の自動車業界で注目すべき動向としては、アライアンスの拡大です。いわゆる「仲間づくり」で、他社と協力することにより、新技術の開発に対応していこうという取り組みです。自動運転、電動化、コネクテッド、AIなどこれら先進技術は莫大な研究費がかかり、1社単独ですべてを賄うのは不可能です。
こうした動向を受け、2019年にトヨタはスズキへHVのシステムの提供を、EVではSUBARUとの共同開発を発表しています。2022年6月には日産自動車と三菱自動車が共同で軽自動車のEVを販売しました。こうしたアライアンスの動きは今後も増えてくると見られ、各社の動きに注目が集まります。
今後、自動車業界は大変革期を迎えます。それは今までの自動車業界とは全く違う業界に生まれ変わるほどのインパクトがあるかもしれません。2020年1月にはソニーが自動運転のEV車を一般公開したように、他業種からの参入も増えるでしょう。時代の転換点にある今、未来の自動車はどうなるのか、今後の動向に注目が集まります。
自動車業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで自動車市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | トヨタ自動車 | 371,542 | ||
| 2 | 日産自動車 | 105,966 | ||
| 3 | ホンダ | 105,935 | ||
| 4 | スズキ | 41,621 | ||
| 5 | マツダ | 38,267 | ||
| 6 | SUBARU | 36,905 | ||
| 7 | いすゞ自動車 | 31,955 | ||
| 8 | 三菱自動車工業 | 24,581 | ||
| 9 | 日野自動車 | 15,073 |
※シェアとは自動車業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで自動車市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ自動車業界の詳細ランキングページにジャンプします。
自動車業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
トヨタ自動車、日産自動車、ホンダ、スズキ、マツダ、SUBARU、いすゞ自動車、三菱自動車工業、日野自動車の計9社
自動車業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。自動車業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。