
製糖業界の動向や現状、シェア、ランキングなどを解説しています。データは2022-2023年。過去の製糖業界の市場規模の推移をはじめ、製糖の出荷金額と出荷額の推移、製糖メーカーの売上高ランキングや三井製糖と大日本明治の統合の動向、各社の取り組みなどをご紹介しています。
業界規模
0.2兆円
成長率
9.8%
利益率
3.4%
平均年収
742万円
製糖業界の過去の業界規模の推移を見ますと、2020年までは横ばいで推移していましたが、2021年、2022年と増加に転じています。
農林水産省の「砂糖及び異性化糖の需給見通し(2022年12月公表)」によると、2022年の国内産糖生産の見通しは前年比10.6%減の70万8千トン、砂糖の輸入量の見通しは前年比7.5%増の105万8千トンとなりました。
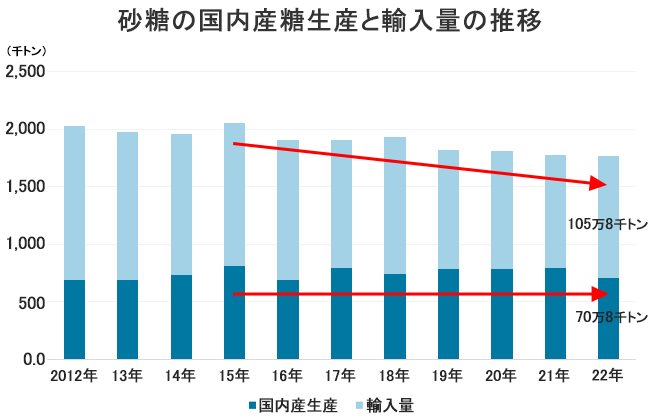
砂糖の国内産糖生産と輸入量の推移(出所:農林水産省、グラフは業界動向サーチが作成)
グラフを見ますと、2022年は国内が前年から8万4千トンが減少し、輸入量は7万4千トンの増加となりました。一方、中長期的には国内産の生産は横ばい、砂糖の輸入量は減少傾向であることが分かります。
近年の製糖業界の動向を見ますと、新型コロナウイルスの影響により、外食の落ち込みや土産菓子などインバウンド減少の影響を受け、業務用ニーズは減少しました。一方で、非常事態宣言の影響により、消費者が家にいる機会が増えたため、家庭用は増加を記録しました。
2021年の製糖業界は、経済再開に伴う業務用の回復が一部で見られ、昨年からは回復傾向にあります。一方で、年後半からは粗糖価格をはじめ、海上運賃や原油価格など生産コストの高騰が響いています。こうした動向を受け、製糖メーカー各社はコスト上昇分を転嫁した値上げを実施しています。
2022年から2023年の製糖業界は、家庭用は減少した一方で業務用の需要が増加しました。また、インバウンドの回復により外食や土産物向けの需要が回復したほか、清涼飲料向けや菓子向けなどの業務用も回復、販売価格も上昇したことで収益は増加しました。一方、円安の進行や輸入国の天候不順の影響で粗糖相場は高値圏で推移しており、砂糖の出荷価格が引き上げられています。
※は製糖関連の売上高。続いて製糖業界の内訳を見ていきます。製糖業界の2022-2023年の売上高ランキングによると、首位はDM三井製糖HD、2位がウェルネオシュガー、日本甜菜製糖と続きます。2位のウェルネオシュガーは日新製糖と伊藤忠製糖の経営統合により、2023年1月に発足しました。
売上高ランキングを見ますと、上位3社の売上高が大きく、とくに首位のDM三井製糖HDの売上高が大きいことが分かります。製糖業界は景気の影響を受けにくく、例年、横ばいが続きますが2021年は前年の落込みから反発、2022-2023年も引き続き堅調に推移、5社中5社が増収となっています。

一般的に、製糖(砂糖)の需要は人口に大きく影響します。国内の人口は今後、減少傾向にありますので砂糖の需要も今後、減少してゆくことが予想されます。さらに今日では代替甘味料の増加や、原材料の上昇、消費者のニーズの多様化など課題も山積みとなっています。
こうした動向を見据え、製糖業界では再編の動きが起きはじめました。
2021年4月には、三井製糖と大日本明治製糖が統合し、持ち株会社「DM三井製糖ホールディングス」が発足しました。両社が統合することで、国内基盤の強化や成長分野への人的資源の優位性が確保されます。
さらに製糖3位の日本甜菜製糖もDM三井製糖HDと資本業務提携を行いました。首位の三井製糖の基盤がさらに強化されることとなりました。
一方、2023年1月には日新製糖と伊藤忠製糖が経営統合し「ウェルネオシュガー」が発足、製糖事業の基盤強化と事業領域の拡大を図ります。
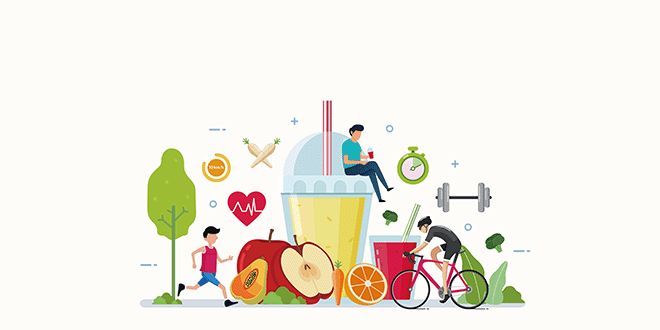
業界首位の三井製糖は、コロナ禍の影響により増えた「家庭内調理ニーズ」に着目。有名料理家とのコラボやSNSを通じたアプローチを展開します。「ととのえオリゴ食物繊維」、「血糖値の上昇を抑えるスローカロリーシュガー」や「嚥下サポート」など健康や高齢者を意識した商品を強化しています。
砂糖と同じ甘さで食物繊維が摂れる三井製糖の「整(ととのえ)オリゴ糖」
業界2位の日新製糖は、腸内環境を良好に保つ「オリゴの王様」を展開。こちらは熱や酸に強いガラクトオリゴ糖を使用しており、紅茶やコーヒーにも使用可能。2020年上半期では前年比5割増と販売が好調です。
市場が縮小してゆく中で、成長する有効な手段は「付加価値の提供」です。とくに日本は今後、高齢化が進むため、「健康」や「高齢」をテーマとした商品は大きく伸びる可能性を秘めています。消費者ニーズを丹念に調査し、的確にアプローチすることができれば、縮小する市場の中で売上を拡大することも可能でしょう。
製糖業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで製糖市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | DM三井製糖HD ※ | 1,385 | ||
| 2 | ウェルネオシュガー ※ | 539 | ||
| 3 | 日本甜菜製糖 ※ | 453 | ||
| 4 | 塩水港精糖 ※ | 260 | ||
| 5 | 東洋精糖 ※ | 135 | ||
| 6 | フジ日本精糖 ※ | 116 |
※DM三井製糖HDは砂糖事業、ウェルネオシュガーは砂糖その他食品事業、日本甜菜製糖は砂糖+食品事業、塩水港精糖、東洋精糖は砂糖事業、フジ日本精糖は精糖事業の売上高です。シェアとは製糖業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで製糖市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ製糖業界の詳細ランキングページにジャンプします。
製糖業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
DM三井製糖HD、ウェルネオシュガー、日本甜菜製糖、塩水港精糖、東洋精糖、フジ日本精糖の計6社
製糖業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。製糖業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。