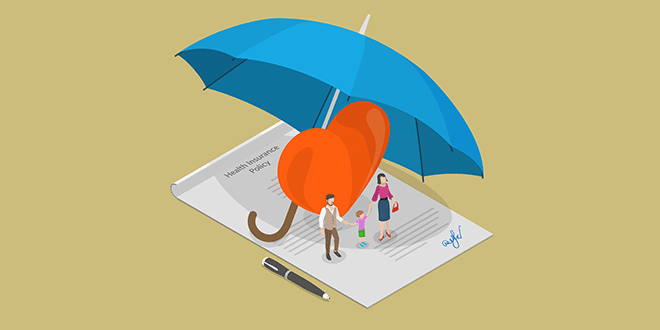
生命保険業界の動向や現状、ランキング&シェアなどを分析しています。生命保険業界の過去の業界規模の推移をはじめ、大手生保の保険料収入の推移グラフ、2021-2022年の動向と業界が抱える課題などについて解説しています。
業界規模
32.6兆円
成長率
-2.7%
利益率
0.1%
平均年収
858万円
生命保険業界の過去の業界規模の推移を見ますと、長期的に緩やかな減少傾向にあります。
以下のグラフは、大手生命保険4社の2021年までの保険料収入の推移を示したものです。
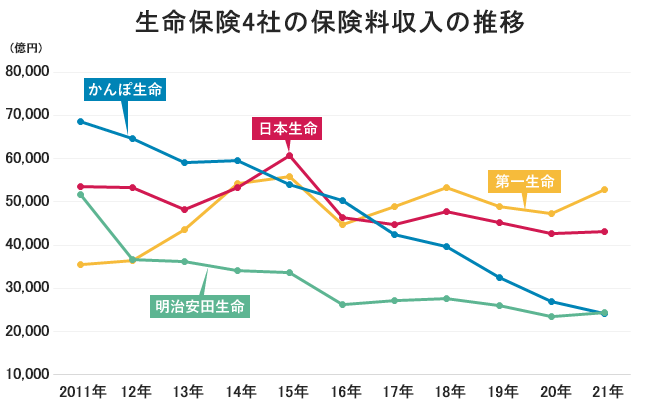
生命保険大手4社の保険料収入の推移(出所:各社有価証券報告書、グラフは業界動向サーチが作成)
2011年から2021年の推移を見ますと、全体的に減少傾向にあることが分かります。各社の2021年(2021年3月決算値)の保険料収入は、第一生命HDが前年比11.9%増の5兆2,919億円、日本生命が同1.0%増の4兆3,079億円、明治安田生命が3.9%増の2兆4,435億円、かんぽ生命保険が10.3%減の2兆4,189億円でした。
2021年の大手生命保険29社の保険料収入の合計は、32兆6,922億円で前年比4.0%の増加でした。前年の2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、生命保険業界は2年連続の減少でした。一方、2021年は増加に転じており、業績は回復しつつあります。
2021-2022年の生命保険業界の動向を見ますと、前年の対面営業自粛の反動が見られたことや、オンラインでの営業活動も組み合わせたことで、新規契約件数と新規契約高がともに増加しました。保有契約件数も前年から増加したものの、満期を迎える契約や死亡保障を抑え医療保障を充実させる近年の傾向から、保有契約高は減少しました。
18年4月には、11年ぶりに死亡率の算出基準となる「標準生命表」の改定が行われました。生命保険各社は死亡保険料を値下げした一方で、医療保険は値上げに踏み切っています。
「標準生命表」とは、男女別で各年齢の死亡率をまとめたもので、保険会社が保険料を決める基準となるものです。前回の07年に比べて全年齢の死亡率が低下し、平均寿命が延びたため保険料の値下げが行われました。
一方、厚生労働省の調査(2022年7月公表)によると、2021年の国内の平均寿命は、男性が81.47歳(前年比-0.09)、女性が87.57歳(前年比-0.14)でした。平均寿命は過去2番目の高水準ではありますが、前年を下回るのは10年ぶりとなります。がんや交通事故などの死亡率の減少が平均寿命を伸ばす一方で、新型コロナウイルスなどによる死亡率の増加が平均寿命を縮める方向に働いているとの発表をしています。
2021年の生命保険業界の売上高ランキングを見ますと。首位が第一生命HD 、2位が日本生命、明治安田生命、かんぽ生命保険、住友生命とつづき、第一生命HDが一歩リードしています。
2021年の生命保険業界は、利益面でも多くの企業が増加となりました。利息及び配当金収入などの資産運用収益が好調だったことや円安効果などにより、企業によっては最高益を記録しています。
2024年から2025年の生命保険業界の主なニュースをピックアップしました。最近の生命保険業界の動向や現状を把握するのにご活用下さい。
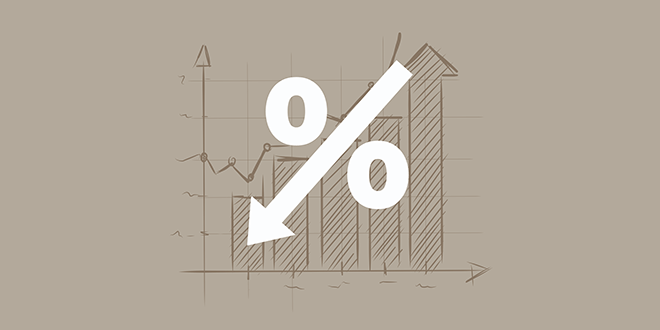
現在、生命保険業界を苦しめているのが「低金利」です。
生命保険会社は、「将来の保険金の支払に充てる財源を確保するもの」という観点から、安全性を重視した運用を義務付けられています。運用には公社債、株式、外国証券などがありますが、運用の主軸は公社債で、主に国債です。
ところが、日銀の長引く金融緩和策によって、国債の利回りが著しく低下しており、運用の主軸である国債で利益を出すことができません。こうした動向を受け、生命保険各社は、償還期限を迎えた国債を外債に充てたり、ESG債など新規分野への投資比率を高めることで何とか対応しています。
さらに、先ほどお伝えした「標準生命表」の改定により保険料の引き下げも行われ、「収入減」、「運用益減」の二重の痛手を受けています。
こうした市況から、長引く低金利の下では予定利率の維持が厳しいとして、企業年金保険の利率を下げる動きが始まりました。第一生命HDは、2021年10月に1.25%から0.25%へと予定利率を引き下げ、また、日本生命でも2023年4月より1.25%を0.50%に引き下げるとしています。
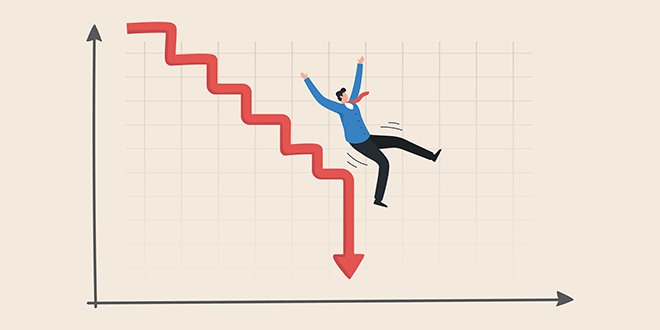
保険業界では、団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」や、団塊ジュニアが60歳以上となり、団塊世代の死亡数が増える「2035年問題」が問題になっています。
今後、少子高齢化や人口減少が進むことで、保険金の支払が増加する一方、契約者は減少するという厳しい状況が予想されます。さらに、昨今の「若年層の保険離れ」も問題となっています。
生命保険業界では、少子高齢化と人口減少による競争激化に備え、各社新会社の設立や国内外の生命保険会社を買収して販路を強化しています。また、低金利の影響を受けにくい「保障性商品」や「外貨建て保険商品」、保険者の健康への取り組みによって保険料が変わる「健康増進型保険」の開発などにも注力しています。
生命保険業界は、今後、国内の人口減少により競争が激しくなると見られています。事業規模の小さい保険会社は経営維持が難しくなり、業界内での再編が増えることも予想されます。
生命保険業界の保険料収入ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで生命保険市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 保険料収入(億円) | シェア | |
| 1 | 第一生命HD | 52,919 | ||
| 2 | 日本生命 | 43,079 | ||
| 3 | 明治安田生命 | 24,435 | ||
| 4 | かんぽ生命保険 | 24,189 | ||
| 5 | 住友生命 | 21,431 | ||
| 6 | メットライフ生命 | 19,056 | ||
| 7 | T&Dホールディングス | 17,819 | ||
| 8 | ソニー生命 | 13,773 | ||
| 9 | アフラック生命保険 | 13,203 | ||
| 10 | プルデンシャル生命 | 10,613 |
※シェアとは生命保険業界全体に対する各企業の保険料収入が占める割合です。シェアを比較することで生命保険市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ生命保険業界の詳細ランキングページにジャンプします。
生命保険業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
第一生命HD、日本生命、かんぽ生命保険、明治安田生命、住友生命、T&Dホールディングス、メットライフ生命、アフラック生命保険、ソニー生命、プルデンシャル生命、ジブラルタ生命、三井住友海上プライマリー生命、マニュライフ生命、東京海上日動あんしん生命、アクサ生命、三井住友海上あいおい生命、オリックス生命、富国生命、エヌエヌ生命、大樹生命、プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命、朝日生命、FWD富士生命、ニッセイ・ウェルス生命、フコクしんらい生命、チューリッヒ生命、メディケア生命、ライフネット生命、アクサダイレクト生命などの計29社
生命保険業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。生命保険業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。