
証券業界の動向や現状、ランキング、売上高シェアなどを研究しています。データは2022-2023年。証券業界の過去の市場規模の推移をはじめ、2020年から2021年までの証券業界の動向や近年のトレンドなどを掲載しています。
業界規模
5.5兆円
成長率
12.7%
利益率
5.4%
平均年収
836万円
証券業界の過去の業界規模の推移を見ますと、直近の2022年は大幅に増加しています。
以下のグラフは、証券大手5社の営業収益の推移グラフです。グラフの推移を見ることで、どの証券会社が伸びているのかを把握することができます。
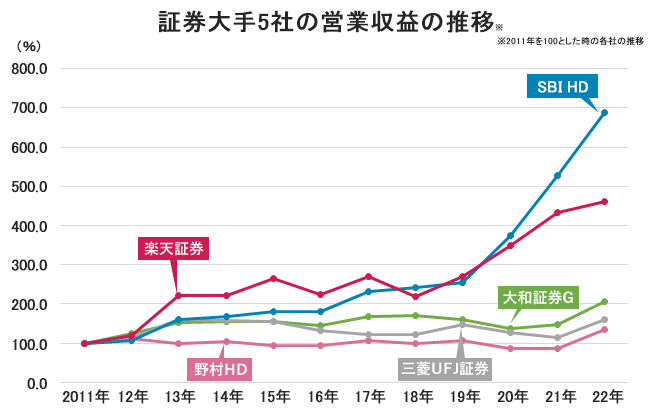
証券大手5社の営業収益の推移(出所:各社有価証券報告書、グラフは業界動向サーチが作成)
グラフを見ますと、楽天証券やSBIホールディングスの「ネット証券」が増加傾向にあるのに対し、野村HDや大和証券などの証券会社は伸びが鈍化しているのが分かります。とくに2020年から2023年にかけてネット証券であるSBIや楽天証券が急上昇しています。(※なお、2021年以降のSBI HDの営業収益については、新生銀行の連結決算が上乗せされていますので、ご留意下さい。ちなみに、新生銀行分を差し引いてもSBIは大幅増を記録しています。)
2022年の証券業界を取り巻く状況は、前年の歴史的な株高による「コロナバブル」の形成から一変、2022年の株式市場は一転して急落しています。市場環境が不透明な状況により投資家の様子見姿勢が続くなど売買手数料に影響がでました。一方、投資信託への資金流入は継続しており運用資産残高が拡大しています。また、ネット証券においては口座数が伸びており、特に若年層の取引が増加傾向にあります。
2022年は欧米を中心とするインフレ懸念から各国の中央銀行が急速な金融引き締めに動き、株価は20~30%の大幅な下落を記録しました。いわゆる金融緩和の巻き戻しの動きです。為替も一時、1ドル150円まで進むなどドル高の局面が続きました。
近年の証券業界のトレンドとしては、個人投資家を中心とした「米国株」人気が顕著に見られました。特にネット証券では、以前よりも手軽に米国株が売買できるようになったこともあり、業績を大きく押し上げています。投資信託でも、株式同様に、外国投信に人気が集中しました。
| 順位 | 企業名 | 営業収益(億円) | |
| 1 | 野村HD | 24,867 | |
| 2 | SBIホールディングス | 9,985 | |
| 3 | 大和証券グループ本社 | 8,660 | |
| 4 | 三菱UFJ証券HD | 4,928 | |
| 5 | 楽天証券 | 954 |
2022-2023年の証券業界の営業収益ランキングを見ますと、首位は野村HD、2位はSBIホールディングス、大和証券、三菱UFJ証券、楽天証券と続きます。首位の野村HDは、個人・法人投資家向けリテール事業と法人向けホール事業を展開しています。2位のSBI HDはネット証券専業の最大手で、SBI証券やネットバンキングなどの金融サービスを展開しています。ネット証券と外国株の取引実績に強みがあります。
2022-2023年の証券業界は、証券大手5社中5社が増収となりました。全体としては前年に比べて増加となっています。
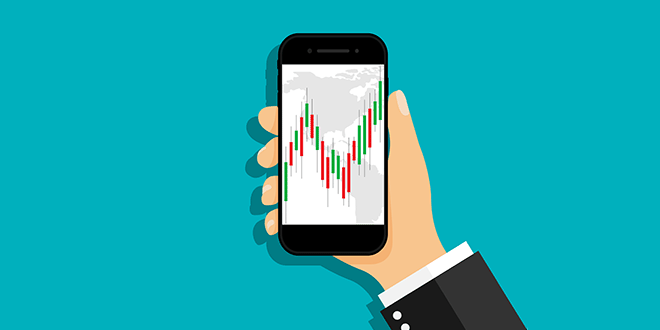
証券業界の業態は主に「店頭型」と「ネット証券」の2つに大別できます。「店頭型」はいわゆる従来からある証券会社で店頭での対面取引がメイン、「ネット証券」はインターネット専業の証券会社です。
近年、証券業界でシェアを拡大しているのが「ネット証券」です。店頭型は実店舗と多くの人員を抱えているため手数料が高いのに対し、ネット証券は実店舗を持たず少ない人員で済むことから、安価な手数料を売りに集客を図っています。業界内では売買手数料の引下げが相次いで起こり、さらには手数料の撤廃を宣言をする企業も出始めるなど手数料における競争が過熱しています。
近年の証券業界の業績においては、「店頭型」の証券会社の業績が伸び悩み苦戦しています。店頭型の顧客である投資家がネット型へ移行したり、高齢化で資産を相続した家族が資金を引き上げるといった事態が起きています。苦戦を強いられた野村HDと大和証券は店舗の統廃合を発表、事業改革を迫られています。
一方で、SBIや楽天、マネックスG、松井証券などの「ネット証券」は堅調な伸びを記録しています。こうした動向を受け、岡三証券や大和証券などの従来型の証券会社もネット証券へ参入。野村HDはLINEと合弁会社を設立しています。
店頭型では高齢者や富裕層が多いのに対し、ネット証券は個人投資家が主要顧客、頻繁に取引を行うトレーダーです。トレーダーは「デイトレード」や「スイング」により比較的に短期に回数を重ねるのが特徴です。安価な手数料が強みのネット証券にとって、頻繁に取引をするトレーダーはネット証券会社には欠かせない存在です。上げ相場はもちろん、下げ相場でも取引を頻繁に行うことから、「買いのみ」の投資家に比べて、手数料収入が安定するといった特徴があります。
ネット証券が台頭し業績を伸ばす中、スマートフォンのアプリで株やFXの売買を行える「新興ネット企業」もじわじわと頭角を現しています。今後も時代の流れからネット証券が主流になるのはほぼ確実で、従来型の証券会社は新たな対策を講じる必要があります。
このように、近年の証券業界は同業他社に加え新規や異業種からの参入、また統合や再編などが行われるなど競争は激化しており、今後も厳しい競争環境が続くと予想されています。
証券業界の営業収益ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで証券市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | 野村HD | 24,867 | ||
| 2 | SBIホールディングス | 9,985 | ||
| 3 | 大和証券グループ本社 | 8,660 | ||
| 4 | 三菱UFJ証券HD | 4,928 | ||
| 5 | 楽天証券 | 954 | ||
| 6 | マネックスグループ | 793 | ||
| 7 | HSホールディングス | 776 | ||
| 8 | 東海東京フィナンシャルHD | 733 | ||
| 9 | 岡三証券グループ | 665 | ||
| 10 | GMOフィナンシャルHD | 465 |
※シェアとは証券業界全体に対する各企業の営業収益が占める割合です。シェアを比較することで証券市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ証券業界の詳細ランキングページにジャンプします。
証券業界を見た人は他にこんなコンテンツも見ています。関連業種の現状や動向、ランキング、シェア等も併せてご覧ください。
野村HD、SBIホールディングス、大和証券グループ本社、三菱UFJ証券HD、楽天証券、マネックスグループ、HSホールディングス、東海東京フィナンシャルHD、岡三証券グループ、GMOフィナンシャルHD、日本証券金融、あかつき本社、松井証券、auカブコム証券、岩井コスモHD、いちよし証券、丸三証券、スパークス・グループ、アイザワ証券グループ、アストマックス、水戸証券、ヒロセ通商、トレイダーズHD、東洋証券、豊トラスティ証券、日産証券グループ、インヴァスト、マネーパートナーズG、第一商品、極東証券などの計36社
証券業界の動向や現状、ランキング、シェア等のコンテンツ(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。証券業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。
証券 営業収益ランキング(2022-23)
| 企業名 | 売上高 | ||
| 1 | 野村HD | 24,867 | |
| 2 | SBIホールディングス | 9,985 | |
| 3 | 大和証券グループ本社 | 8,660 | |
| 4 | 三菱UFJ証券HD | 4,928 | |
| 5 | 楽天証券 | 954 |